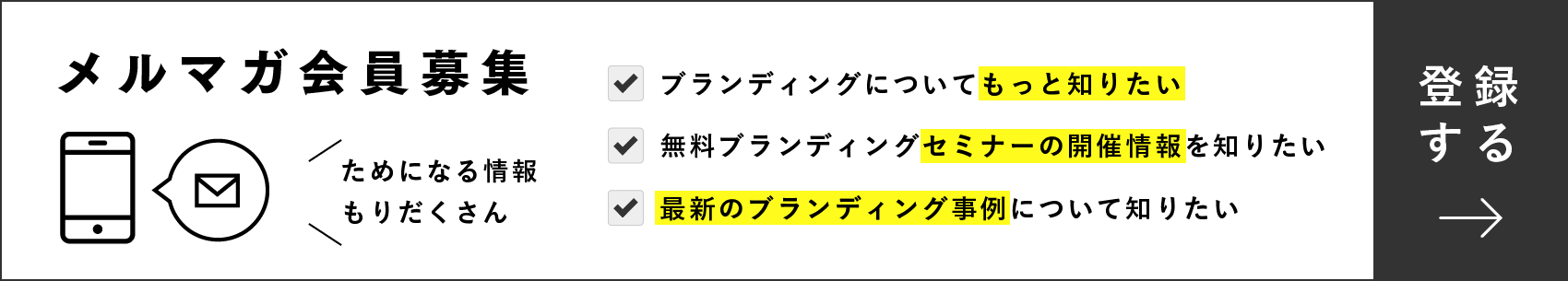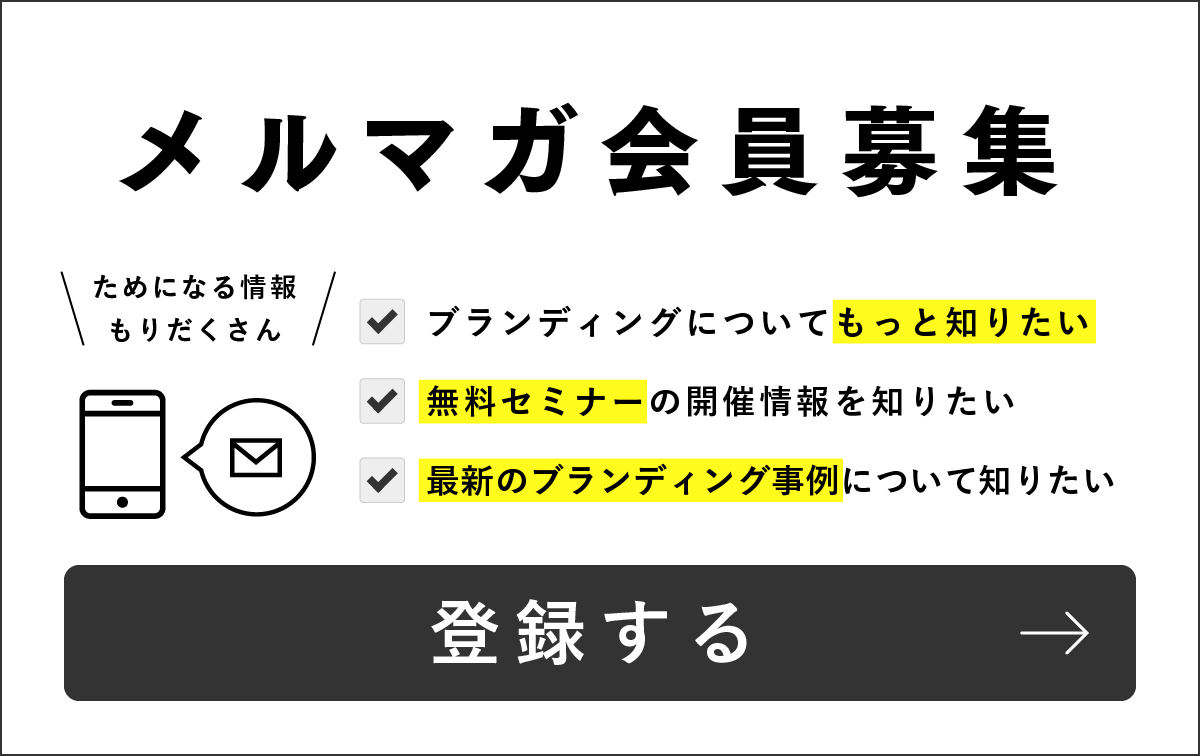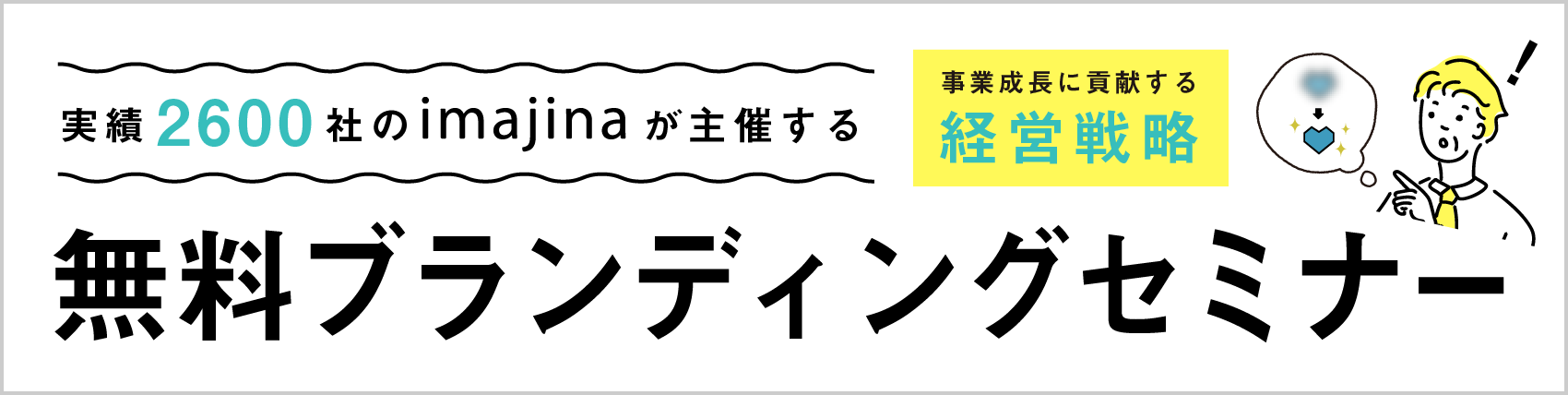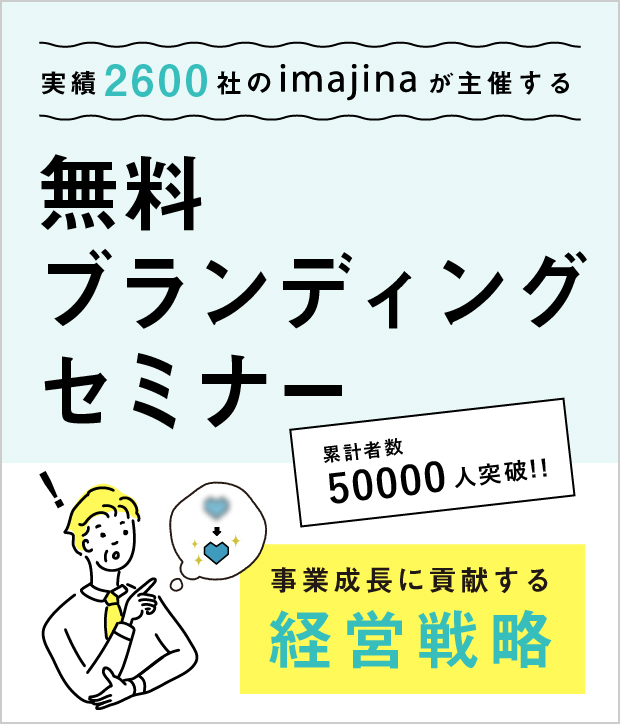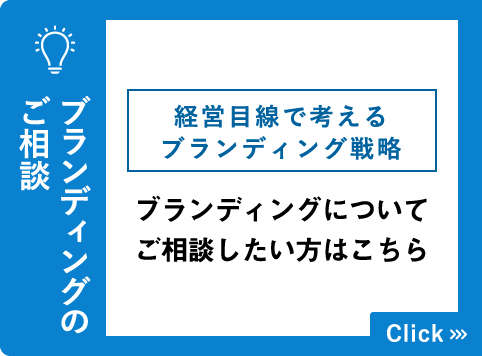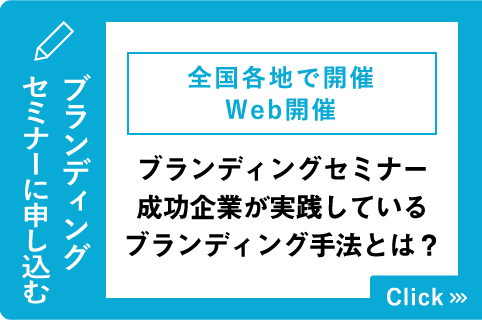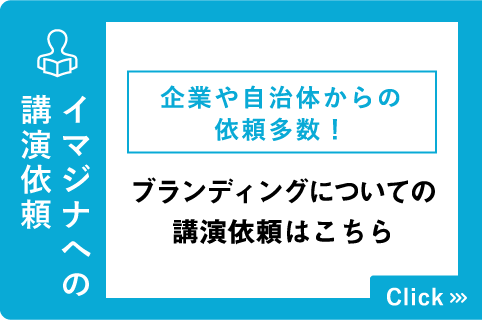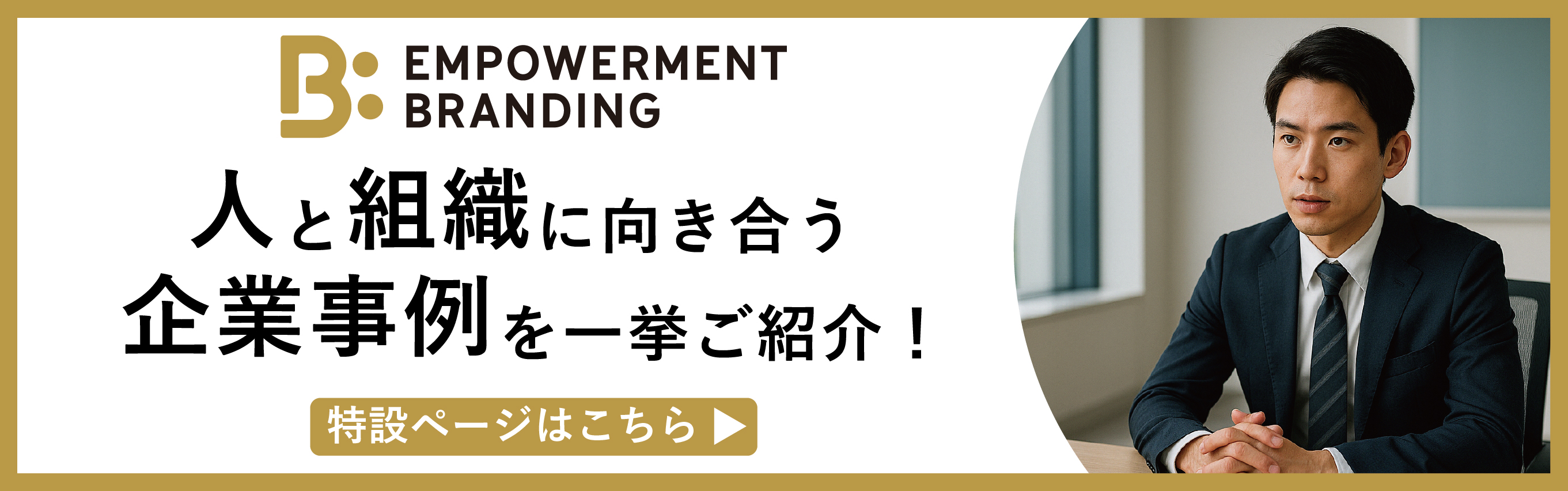Hot HR vol.131 -インドの人材マネジメントのツボ
2014/03/06(最終更新日:2021/11/12)
==================================================================
5分で分かる最新人事トレンド
==================================================================
前々号のvol.129では、日本の中小企業の海外展開の目的は、グローバルにおける様々な経済環境の変化から多様化し始めていると述べた。もう少し内容を整理してみよう。
ジェトロの調査資料によると、日本企業の海外進出目的は次の6パターンに分けられる。
1.新規市場を開拓したい
2.生産コストを削減したい
3.大口取引先からの要請
4.安価な部品・商品の調達
5.新規事業を立ち上げたい
6.海外の高度で豊富な人材を活用したい
(ソース:ジェトロ(日本貿易振興機構))
海外進出前に様々な観点から検討する必要があるが、特にHRに絞ってみると次のような目的別チェックポイントが浮かび上がる。
1.【全ての海外進出において】
自社の海外進出体制、とりわけ海外に派遣しマネジメントを任せられる適材はいるか? また、進出先の人件費や労働者の質、労働慣習、労働関係法規制はどうなっているか?
2.【特に生産コスト削減目的での海外進出の場合】
急速な賃金の上昇や物価の高騰リスクを長期的視野で分析し、見極めているか?(年率10%以上で賃金が上昇している国の場合、10年後には賃金は2.5倍以上に跳ね上がる)
3.【特に高度で豊富な人材(ソフトウェア開発等)の活用を目的とする海外進出の場合】
転職志向が日本より強い国もあることより、高度な人材の引き留め策を準備できているか?
4.【全ての海外進出において】
労使紛争等の予想外のリスクが発生した場合、ここまできたら撤退するという基準を予め決めているか?
本日は、上記チェックポイントを踏まえて、特に今後日本企業の進出ラッシュが予想されるインドにおける「人材マネジメント」と「労使紛争」について触れる。
■インドの人材マネジメントのツボ
インドはまだ多くのインフラが未整備であり、例えば法律面では州法が複雑でビジネス上の障害
となっている。だがそんなハンデを上回る経済成長率があり、進出する日本企業は2009年の627社から2012年には926社(2012年10月時点)へと激増し、2013年には1、000社を超えるものと見られている。日本企業にとっても大きく注目を集める魅力ある市場となっている。
人材マネジメント面から見ると、インドでは非常にヘッドハンティングが盛んであり、人材の流出を防ぐシステム作りがツボといえる。
まずは適切な業績評価制度の導入である。インド人はロジカルな議論を好み、向上心が旺盛な傾向がある。そんな彼らにとってはロジカルで一貫した“業績が給与と連動する人事制度”が必要である。やる気を高めるための制度作り、すなわち彼らの関心が高い、報酬や福利厚生などの制度を整えることが重要となるだろう。
加えて各種インセンティブを設定する際にも、ただ制度を作るのではなく、長期スパンでのインセンティブを設けて人材の引き留め策を講じることが大切である。また、組織の成果が給与へ反映する仕組みを作って、人材の流出を防ぐ工夫をすることも肝要である。
インド人にとって日本企業における問題点は「昇進の機会が少ない」「閉鎖的な雰囲気」といったことが言われており(2009年4月1 日『アジアビジネスの最前線』より)、これらを解決すべく本社人事部と現地マネジャーは連携して、人事インフラの整備をしなければならない。
上級管理職登用への透明性や組織へ大きく関わっていける人材開発プログラムなど、他企業との差別化を図り、リーダーの育成を推進すべきだろう。
■インドにおける労務問題
2012年7月にスズキ自動車のインド子会社、マルチ・スズキ社のマネサール工場で7月に起きた暴動は、インドに進出している日系企業に大きな衝撃を与えた。原因の一つに正規雇用と期間限定の契約工の賃金格差(同じ労働なのに3倍の格差)や労働関連法による保護格差があり、正規雇用の従業員が加盟している労働組合が契約工の待遇改善を求めて、暴動前に3度もストライキを断行していたとのことである。その他、労務問題をインド人管理職に任せきっていたことやカースト問題等もあったようである。労務問題は多くの要因が複雑に絡む問題であるので、できるだけ早期に解決することが肝要であり、そのために日本人駐在員が日頃より心掛けておくべきポイントは次の通りである。(ソース:社団法人日本在外企業協会)
1.日頃より労使間で緊密なコミュニケ―ションを取る。
2.インド人管理職に仕事を任せる、しかしインド人管理職任せにはしない。
3.トラブル、紛争が起こっても冷静に対処し、適法的に行動する。
4.規則、ルールは文書化して保存する。
5.赴任地はインドであり、異文化圏であることを理解する。
■おだてのマネジメント
最後に、インド人の気質を理解してマネジメントするツボも紹介しておきたい。
すなわち、インド人には「おだてのマネジメント」と呼ばれる“褒めて、褒めつつ仕事内容を確
認していく”手法が基本である。インド人には権威志向、認知志向が強い傾向があるからである
(株式会社オリエスシェアードサービスのリサーチより)。
たとえ少し問題のある社員であっても皆の前では「よくやってくれている」と述べ、叱るときは別室で行うことがセオリーだ。日本人の場合、結果を出した社員であっても「こんなことで満足してはダメだぞ」と発破をかける例もあるが、インド人に対しては存分に褒めよう。