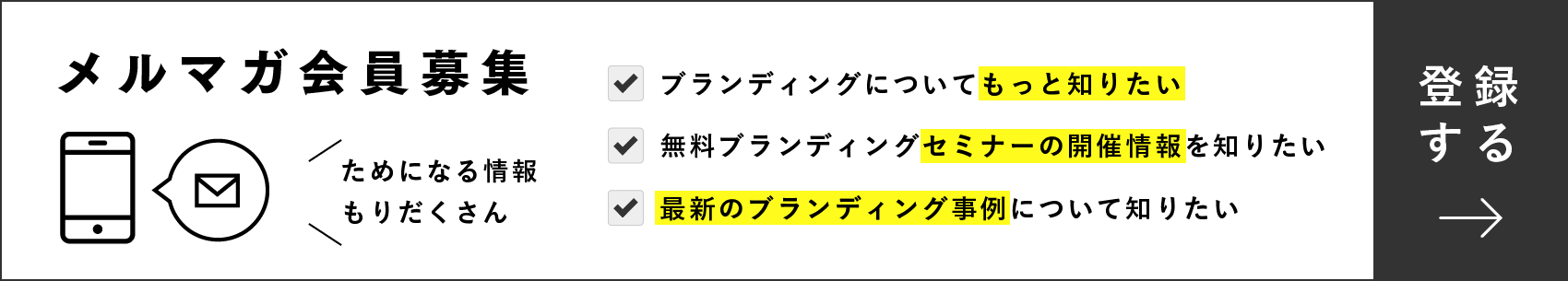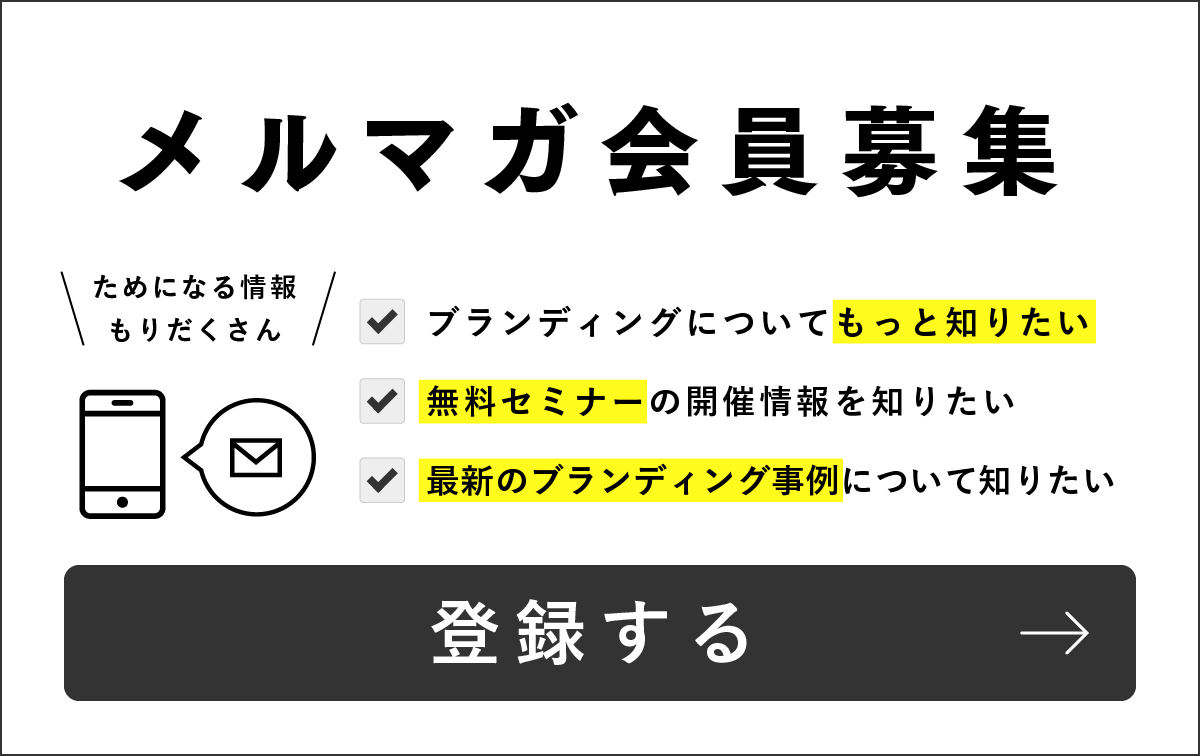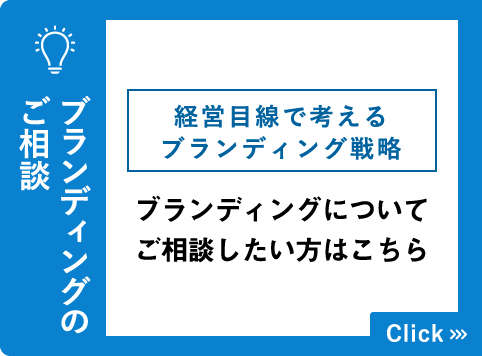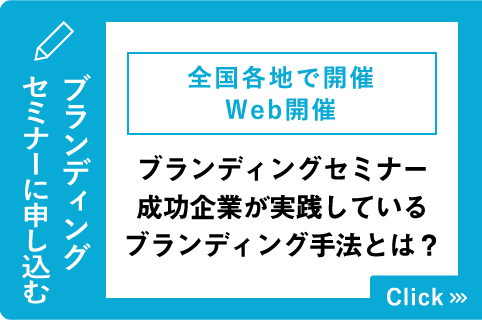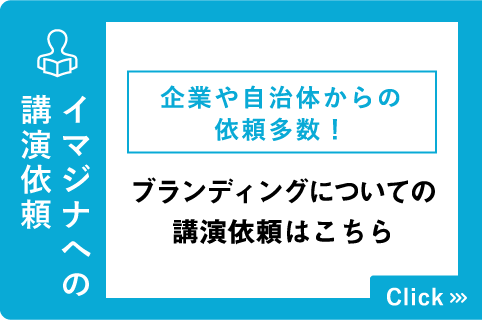レッドブルのための市場は存在しない。我々がこれから創造するのだ。
2016/04/18(最終更新日:2020/07/17)

56億本――。これは2014年度における「Red Bull」の全世界への出荷本数である。
青と銀のカラーの上に赤で描かれたブランド名と、角と角をぶつけ合う牛のロゴを見たことがない人はおそらくいないだろう。一度見たら忘れない、スポーツドリンクでも栄養ドリンクでもない「エナジードリンク」という新しい市場を作り上げたモンスターブランドの缶デザインだ。
日本でも学生から社会人まで多くの人に飲まれており、抜群の認知度と好感度を誇る。しかし同ブランドを運営するRed Bull社に関して実態を知っているものは、そう多くはいないと思う。それもそのはずで、同社は未上場企業のため情報開示もされていないし、メディアに関係者が出ることも方針上少ない。ゆえに関連書籍等も少ないため、なかなか情報が表に出てこないのだ。
ここにRed Bullの強さがある。その知名度と不釣り合いなほどにミステリアスなイメージを商品に持たせることで、かえってブランドの魅力が増し、結果として長年にわたり飽きられない商品を作ることに成功している。顧客の趣向が細分化し、商品ライフサイクルが短くなる現代において、これは稀有な例ではないだろうか。強いブランドを創造するヒントが同社の戦略には隠されている。
実は現在のRed Bullは、タイのある清涼飲料水が「もと」となっている。その清涼飲料水は日本でいう栄養ドリンクのようなもの。これに惚れ込んだRed Bull社社長ディートリヒ・マテシッツが販売権を獲得したのが全ての始まりだった。彼は商品に改良を重ね、現在のRed Bullを開発した。
ディートリヒ・マテシッツ。オーストリア人である彼は、ユニリーバ社の子会社でマーケティング・マネージャーとして働いていた。そんな彼を起業へと奮い立たせたのは、なんと日本の大正製薬社だという。たまたま雑誌で見た日本の高額納税者の企業リストの中に、SONYやTOYOTAに交じり聞いたことのない会社名がある。それがリポビタンDを開発する大正製薬社だった。同社は決してグローバル企業ではない。そんな企業の経営者が、世界2位の経済大国(当時)で高額納税者になることが可能なのかと彼は深い感銘を受けた。またそれは同時に、欧米での栄養ドリンク市場の開拓に無限の可能性を感じた瞬間だった(欧米では日本やアジアほど巨大な栄養ドリンク市場は存在していなかった)。当時38歳のマテシッツ氏は、自身が勝負する土俵を見つけたのだろう。それ以来、彼は栄養ドリンク研究に没頭するようになる。
Red Bullの強みはなんだろうか。それは紛れもなく、徹底して計算しつくされたブランド戦略にある。創業当初から明確なブランドアイデンティティを持ち、それに沿ったマーケティングを展開してきた。例えば「レッドブル、翼を授ける。」という商品キャッチコピー。これは一切商品の効能の説明をしていない。エナジードリンクであるため成分構成自体も十分売り物になるのだが、広告戦略においては機能、ましてや味には一切言及しなかった。訴えるものはイメージ、価値、思想である。それらを全面に打ち出すことで「飲むとパワーをもらえる」という精神的な充足感を与えているのだ。
また同社のプロモーションは独自キャンペーンが多い。通常、企業は広告代理店等を通しイベント等のスポンサーになるが、彼らは自前でイベントを興す。なんと自社で企画・運営を行うのだ。しかも彼らの開くイベントは、他の企業がスポンサーに付きづらいエクストリームスポーツ関連が多い。確かに「翼を授ける」イメージにはもってこいだ。またそれをメディアが取り上げた際は、通常のイベントスポンサーとは比較にならない広告効果が見込める。配信されるのは興行と、自社のロゴと商品だけなのだから。

もちろん、それらにかけるマーケティング予算は膨大になる。一説によると同社の売上高の3分の1に上ると言われているが、なぜマテシッツ氏はこれほどまでにブランディングを追及するのだろうか。
それはマテシッツ氏が「ブランドの構築は一朝一夕にはならない」ことを熟知しているからだ。商品のイメージ構築から販売方法、プロモーションに至るまで、綿密なコミュニケーション戦略を組み、それに忠実な計画策定と実行を行っている。これだけの規模でありながらも、マーケティングに関しては同氏が責任者となり指揮を執っているという。ましてや、広告を代理店に丸投げするなど一切ない。明確なビジョンを持ち、商品特有の世界観を徹底構築することが、他社との差別化に繋がることを知っているからだ。そのため、同市場には類似品が多数出回っているが、Red Bullの牙城に迫るものは存在しない。
80年代半ばに登場した魅惑的なドリンクは、瞬く間に世界を席巻し、今までにない市場と強固なブランドを作り上げた。それと同時に、ブランド構築に必要なのはビジョンと意思と行動力であり、歴史ではないことをマテシッツ氏は証明した。
「この市場には既に多くのプレイヤーがいるから参入するのは無理だ」「歴史も知名度もないから消費者に広まらないだろう」。自社商品のブランド戦略を考えた際にこのような「常識」が頭をよぎることがあるが、Red Bullはそれらの意見をすべてひっくり返す。このような台詞をマテシッツ氏が聞いたら、どう感じるだろう。
彼が独立直後に作ったプレゼン資料には「Red Bullのための市場は存在しない。我々がこれから創造するのだ」と書かれている。ほぼ0から商品を立ち上げ、市場の創造とゆるぎないブランドを構築した同氏から、日本企業が学ぶことは多い。
Red Bullのように世界中で強く支持され続けるブランドが21世紀の日本企業から登場することを、筆者は切に願う。