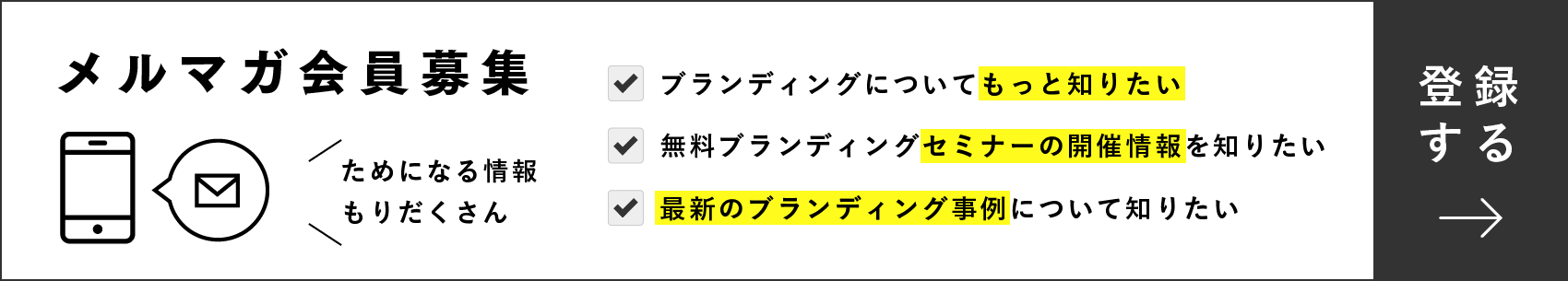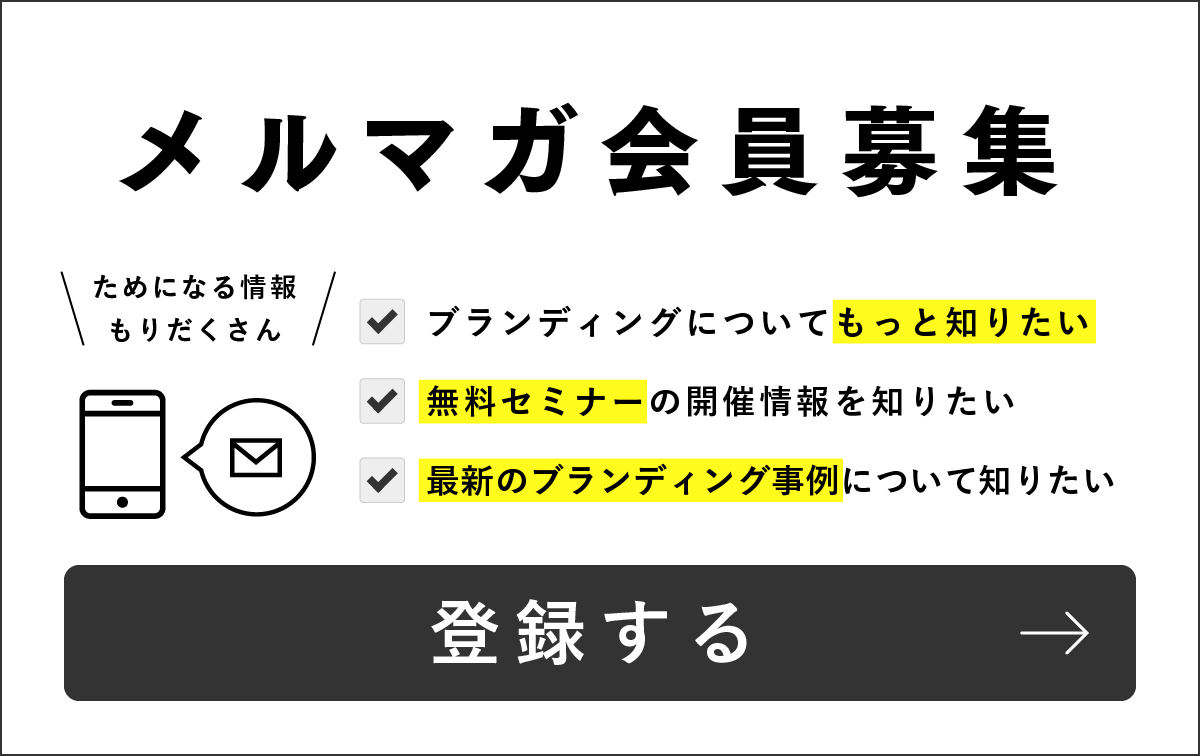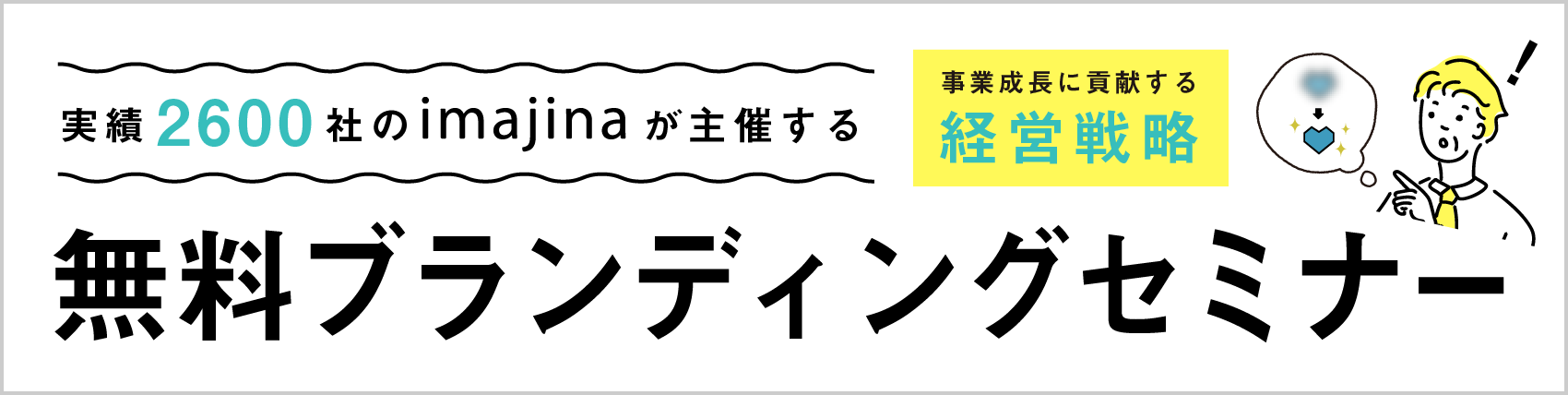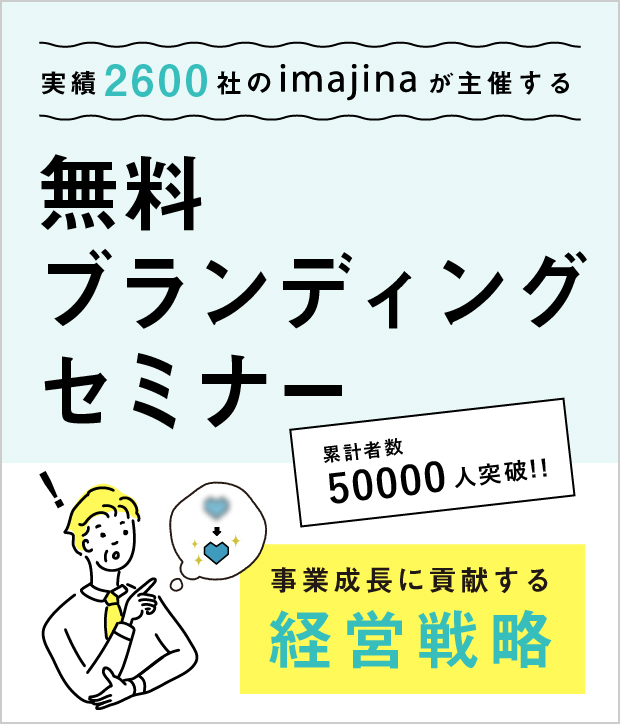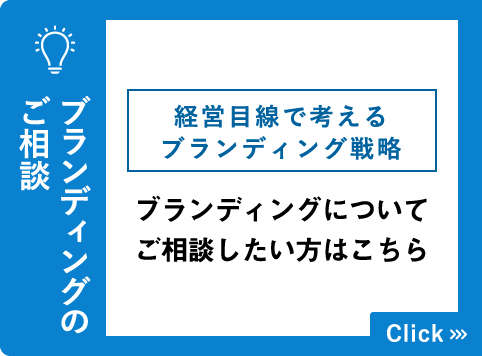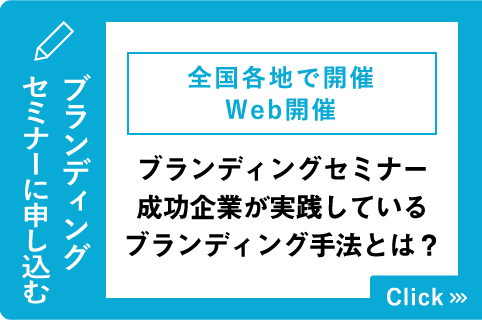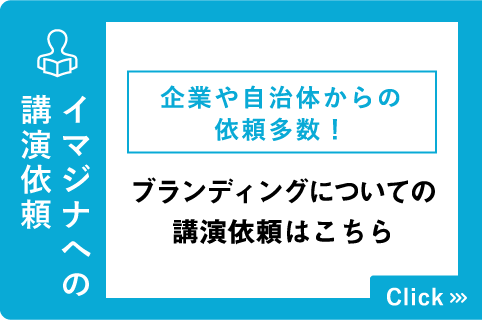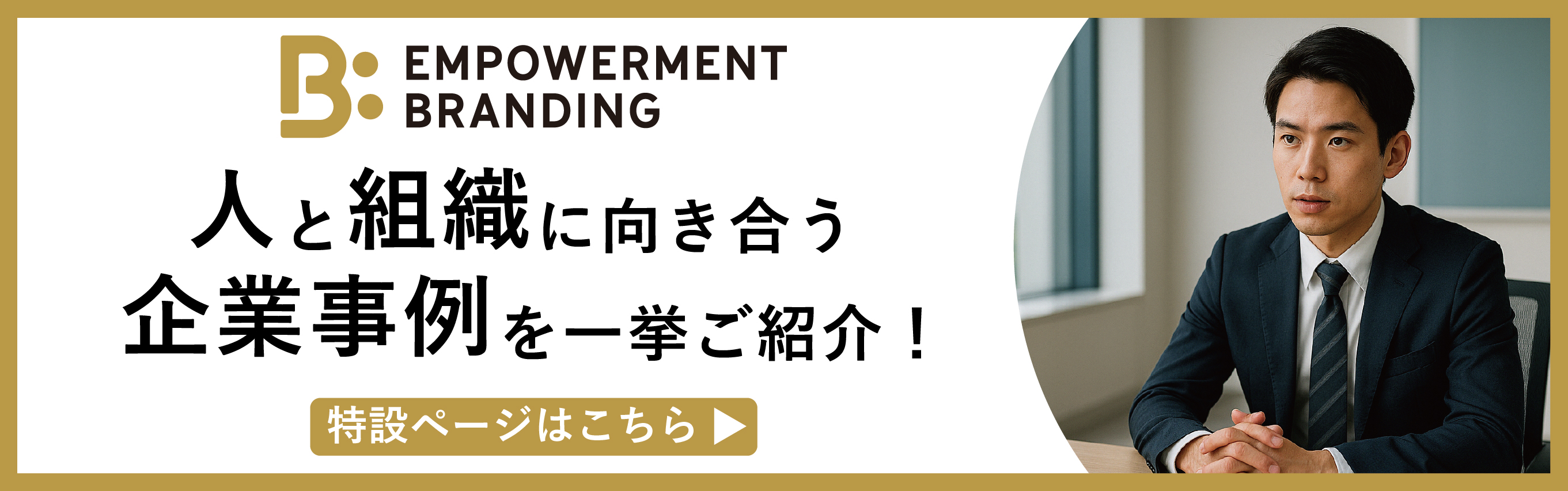株式会社イマジナ 代表取締役社長の関野です。
「リーダー」。
言葉の定義としては「指導者」「統率者」「先導者」。
本メルマガでは、現役の会社経営者であり、同時に企業の課題解決に向けた伴走者として今まで2850社を超える企業の内情を見てきた私自身が今、全国のリーダーにお伝えしたいことを語らせていただきたいと思う。
今日は、「良い仕組み化、悪い仕組み化」というテーマでお話ししよう。(昨日は「良い属人化、悪い属人化」というテーマで配信しているので、まだ読まれていない方はぜひ、併せてお読みいただきたい。)
組織改革の第一歩!!ブランディングセミナー
企業の命運を分けるのは「何を」仕組み化するか
昨今は空前の仕組み化ブーム。
「仕組み化すれば業務効率が上がる」「個人に依存しない組織づくりを」など、ネットニュースの見出しにも書店のビジネス書コーナーにも「仕組み化」の4文字が躍る。
脱・属人化、これからは仕組みで勝つ時代だ!という主張に問いかけたいことがひとつ。
「企業にとって、”何を”仕組み化するのが最も良いと考えますか?」
この「何を」次第で、企業の未来は真逆のものになるから恐ろしい。
今日のタイトルのとおり、仕組み化にも良し悪しがある。
まず「悪い仕組み化」とは何か。これはズバリ、社員の能力や思考力が育たなくなるような仕組みを適用することだ。業務やマネジメントのマニュアル化と言ってもいい。
もちろん、仕事をする上でも単純作業に近い業務など、マニュアル化が必要な部分は少なからずある。しかし、正解が存在しないゆえに、創意工夫を絶やさず、常に試行錯誤と改善を続けていく必要があることを「仕組み・マニュアル」に当てはめ、誰でも同じようにやらせようとしてしまっては、既存の示されたやり方に依存し、誰も「マニュアル以上」を生み出そうとしなくなってしまう。
一時的には全員が同じクオリティを出せるようになって良い影響が出るかもしれない。しかし、それ以上の進化が見られないのであれば、そこに未来は臨めない。
企業にとって、現状維持は衰退と同義だ。
では、「良い仕組み化」とは何か。
企業が文化として根づかせるべき仕組みとは、「社員が自分の頭で考えるようになる仕組み」だ。そのような教育体制と言ってもいい。
たとえば、マネジメントの仕方ひとつとっても「こういう言葉はこう言い換えて、こういうフィードバックはこのタイミングで…」などという小手先のテクニックで考えてはならない。当たり前のことだが、相手となる部下は性格も考え方もそれぞれ異なるため、全員一律のコミュニケーションを行っていては伝わるものも伝わらないからだ。
代わりに、部下の見るべきポイントを決めて、それを仕組みとして導入し、社風になるまで実践していく。「この部下を褒めるには人前がいいか、個別がいいか?どんな価値観を持っていて、どんな言い方だと共感してくれやすいか?」などなど…
そうしたマネジメントのもとで育った部下は、やがて自分の部下にも同じようなマネジメントを行う。こうして、社内に「人が育つ好循環」が生まれる。
要するに、運用する側も思考力を必要とする仕組みでなければならないのだ。そうでなければ、会社全体としての思考力がスケールアップしない。
その「仕組み」は、思考停止の種にならないか?社員の成長につながるのか?
何らかの仕組みを取り入れようとする際にはぜひ、この問いを思い出していただきたい。