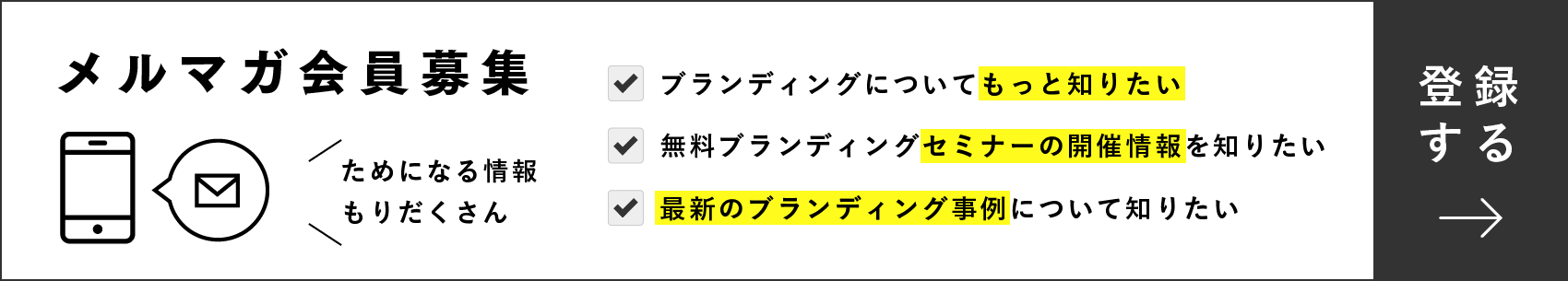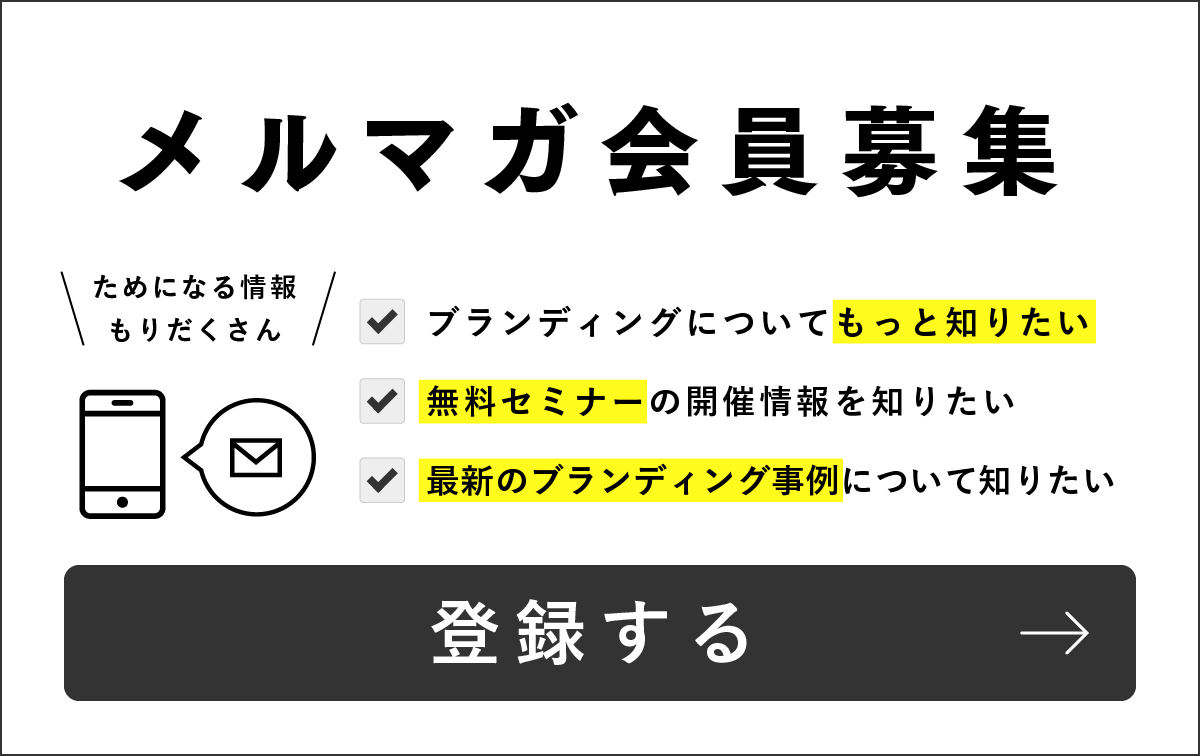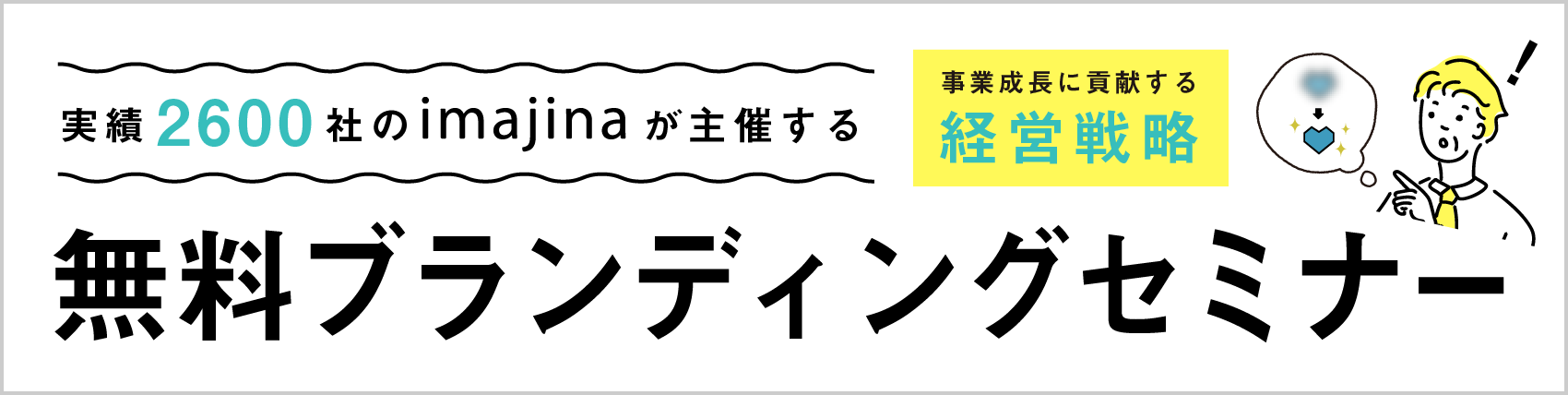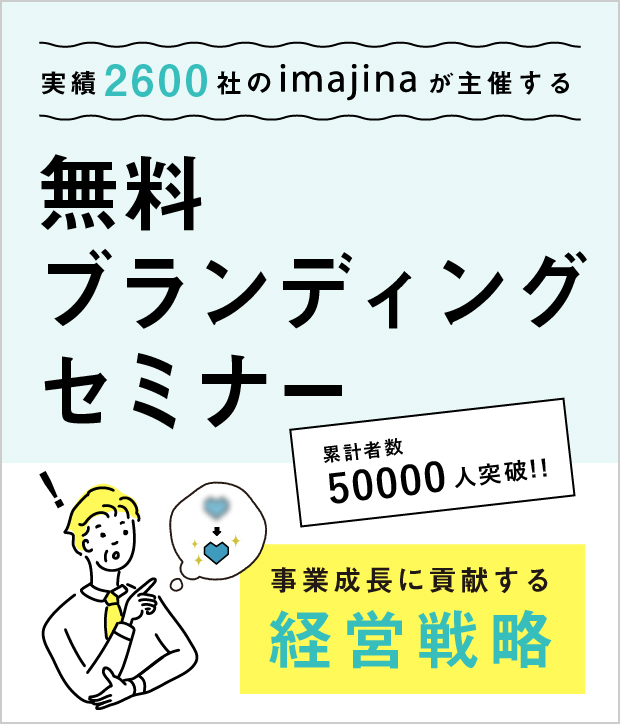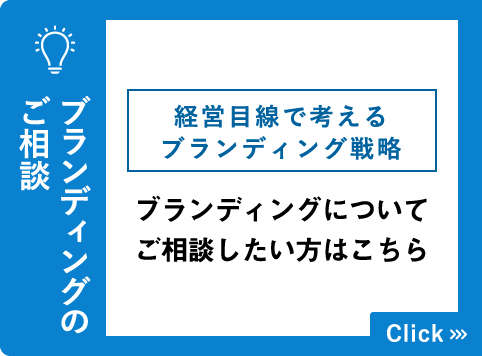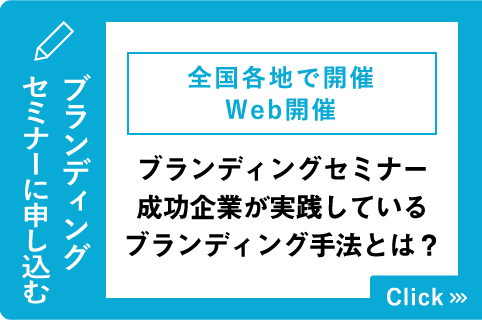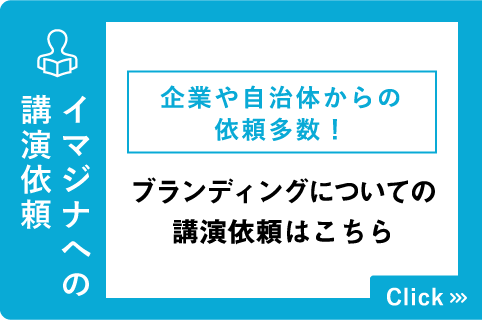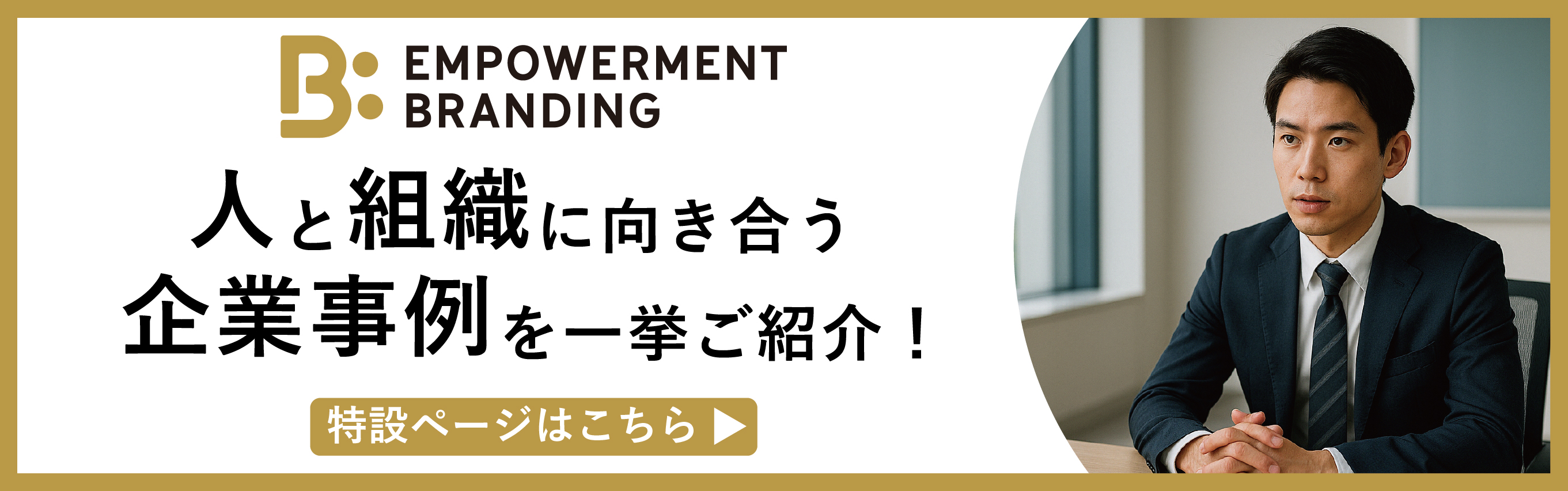株式会社イマジナ 代表取締役社長の関野です。
「リーダー」。
言葉の定義としては「指導者」「統率者」「先導者」。
本メルマガでは、現役の会社経営者であり、同時に企業の課題解決に向けた伴走者として今まで2850社を超える企業の内情を見てきた私自身が今、全国のリーダーにお伝えしたいことを語らせていただきたいと思う。
今日は、「なぜ、部下は指示を守れないのか」というテーマでお話ししよう。
”なぜ”を大切にする企業は伸びる
「ちゃんと言ったのに、期日までにやってくれなかった」
「何度も指示を出しているし、そのときは『わかりました』と言っているのに…」
社員や部下に対してこのように感じたことのある方は多いだろう。
同じ言語でコミュニケーションをとっているはずなのに、なぜこうした事態が起きてしまうのか。
ここで、私も含め「伝える側・指示を出す側」のリーダーがまず理解していないといけないことがある。
それは、「伝える」と「伝わる」は違うということだ。
基本的に、人の行動には理由が伴っている。自主的に行動を起こすとき、完全に何の理由もなく何かすることは少ないだろう。
他人から言われたことでも同じだ。それを「なぜ・何のためにやるのか」がわからなければ、どれほど重要なことなのか、そもそも本当にやる必要があるのか、判断できないから動けない。
つまり、部下に指示を出すときは、やってほしいことに加えて明確な理由や目的をきちんと伝えることが不可欠なのだ。
なぜ、それをやってほしいのか。どのような背景でそのタスクが生まれたのか。なぜ、その期日なのか。結果として何につながるのか。
細かく伝えるには勿論、ただ一言で済ませる指示より時間も労力もかかる。伝える側の言語化能力も問われる。しかし、理由なく「とりあえず言われたからやる」で終わってしまう部下と、最終的な目的や意義を意識しながら動ける部下、どちらが企業に発展的かつ明るい未来をもたらすのかは明白だろう。
全体的なイメージがわからないまま「これ、いつまでにやっておいて」と言われたとしても、部下は納得しない。口では了承の意を伝えるが、本当にやらなければならないという必要性を感じることはできないだろう。
部下がその仕事をする本質的な理由は、「社長や上司に言われたから」ではないはずだ。
本来の目的まで理解した上で取り組んでもらうためにも、リーダーは物事の背景や理由を伝える責任がある。
指示がきちんと納得を伴って伝わるようになり、部下の行動のスピードや精度が上がれば、コミュニケーションコストも減る。何度も同じ指示をしたり、部下と認識がズレていたことにより全く想定とは異なるアウトプットが出てきて最初からやり直したり、なんていう手間もかからなくなる。
1500人程度の規模の企業だとコミュニケーションのミスによる損失額は年間3億円にのぼるというデータもあるくらいだから、侮れない。
電気代を抑えるためにオフィスの節電に気を配るのも大事だが、コミュニケーションの質を向上させるという部分は、人々が思っている以上に組織にとってプラスに働く分野なのだ。
マネジメントの肝となる、上司・部下間のコミュニケーション。
セミナーにてさらに具体的に重要性を解説しているので、気になった方はぜひ足を運んでいただきたい。