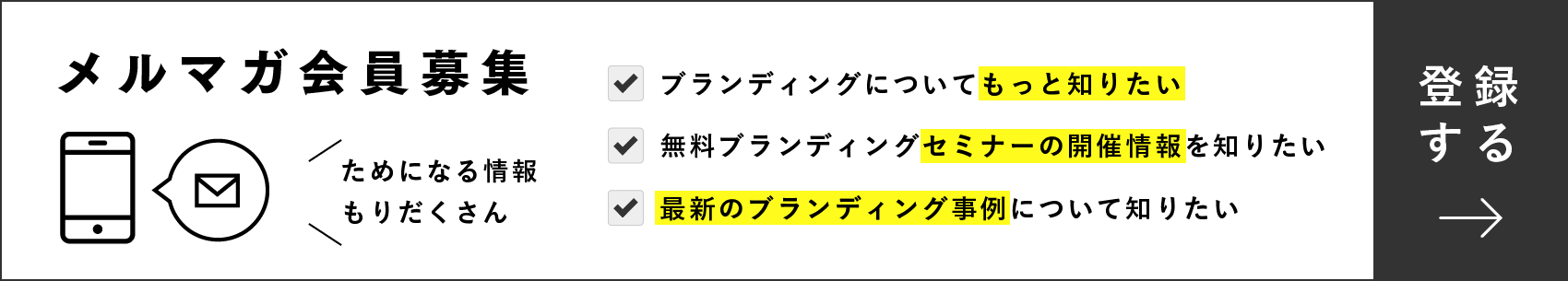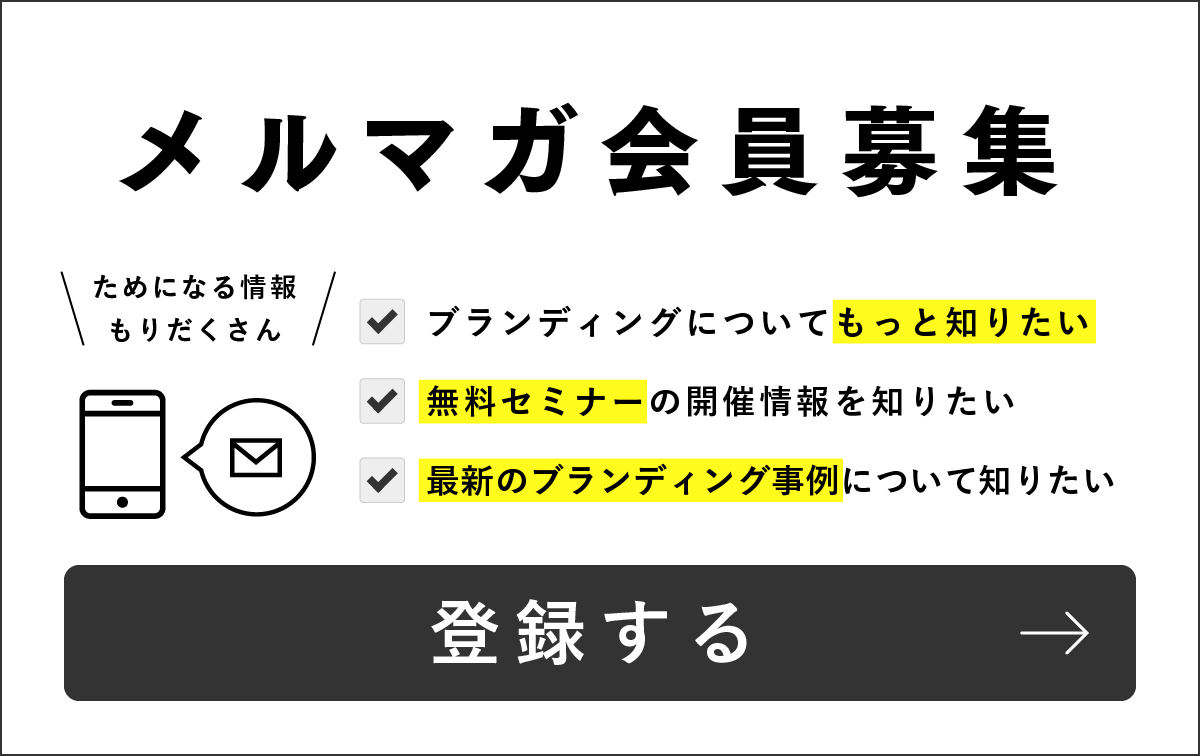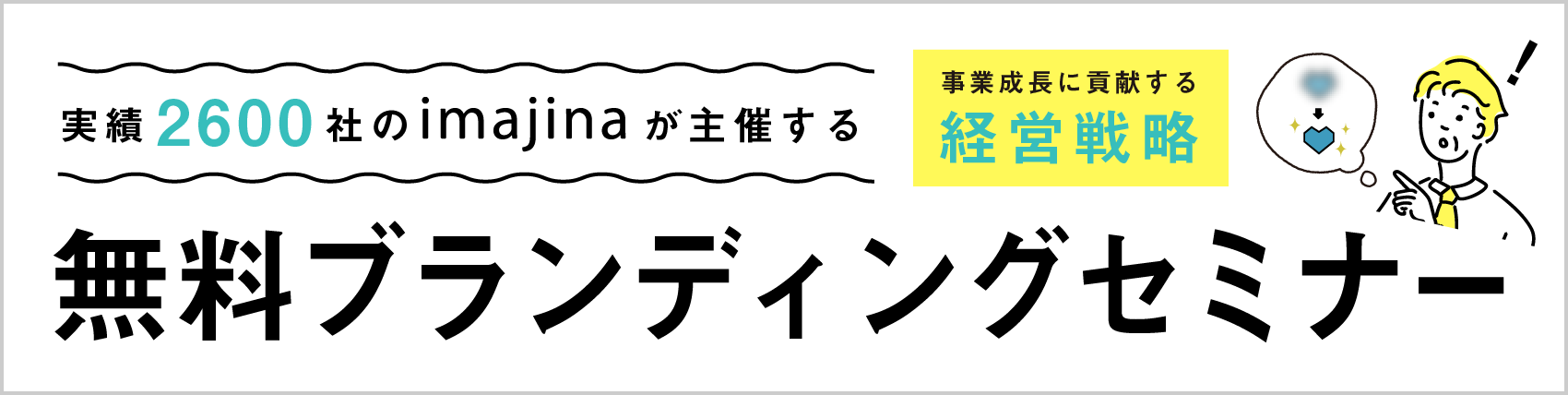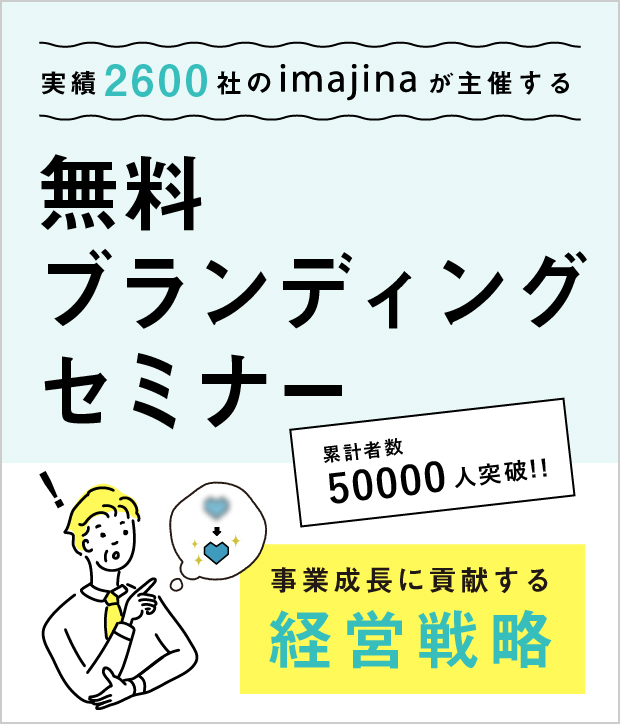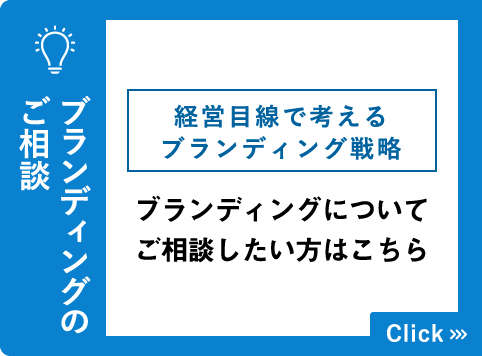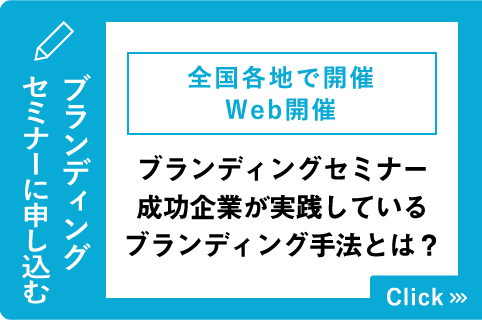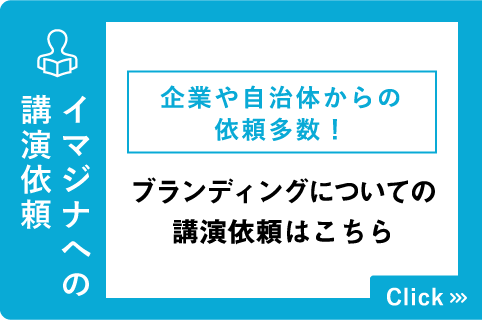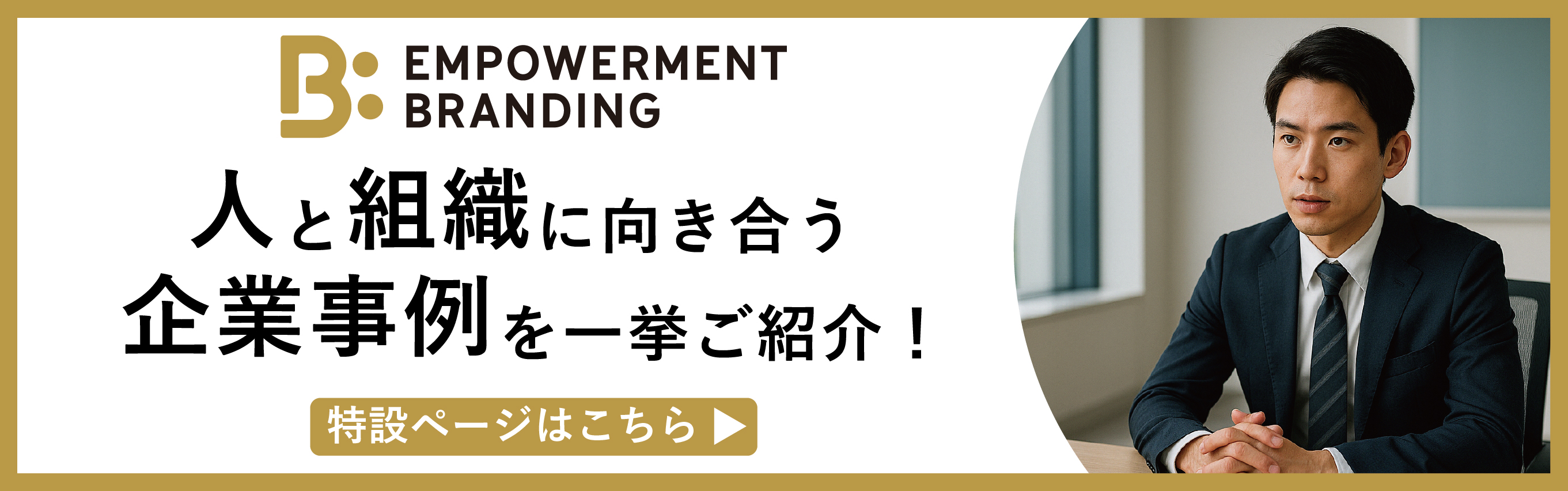総務省によると、1年間に日本で出版されているビジネス書は約70000タイトル。
その中の大きなジャンルのひとつとして、マネジメント書がある。理論から実践、心構えを説いたものまで内容は幅広い。
マネージャー層と若手世代の価値観の乖離、加速するハラスメント問題などを背景に、世の中全体でマネジメントの手法やマインドセットに対する需要が高まっている。
しかし、本や動画で知識を身につけ、試行錯誤しながら実践していけばマネジメントで必ず良い結果を出せるのだろうか?
少し話は逸れるが近年、日本の子どもたちの学習意欲が年々低下していることはご存知だろうか。
ベネッセと東京大学の共同研究によると、小学生から高校生までどの層を調査しても、「勉強しようという気持ちがわかない」と回答する率が急激に増加している。
そして同時に、PISA国際学力テストにおける日本の成績は下降の一途をたどっている。
意欲の低下に比例した、学力の低下。このように、学ぶことに対する主体性を失いつつあるのが現代日本の若者なのだ。
学びに対する主体性が低いという状況は、大学生もさして変わらない。日本の大学生が進学する動機のうち実に半数を占めるのが「就職のため」というもの。
大学進学が、学びを深める以前に大卒資格を得るための表面的な手段と化してしまっていることも否めない。
このような現状を踏まえ、部下世代の若手について考えてみてほしい。マネージャーやリーダーがまず認識しておかなければならないのは、「彼らは学びを受け入れる姿勢や意識がそもそも弱い」という前提の部分なのだ。
すばらしいマネジメントスキルをもって接したとしても、相手側にそれを受けて自身の成長に活かそうという考えがなければ変化には結びつかない。
令和のマネージャーに求められるのは、そうした部下世代の前提の意識から変えていくコミュニケーションなのである。
プロフェッショナルのピッチングコーチは、選手から「教えてください」と頼まれるまで指導しない。教えを受ける側の姿勢が重要なのは、どこの世界でも共通なのだ。