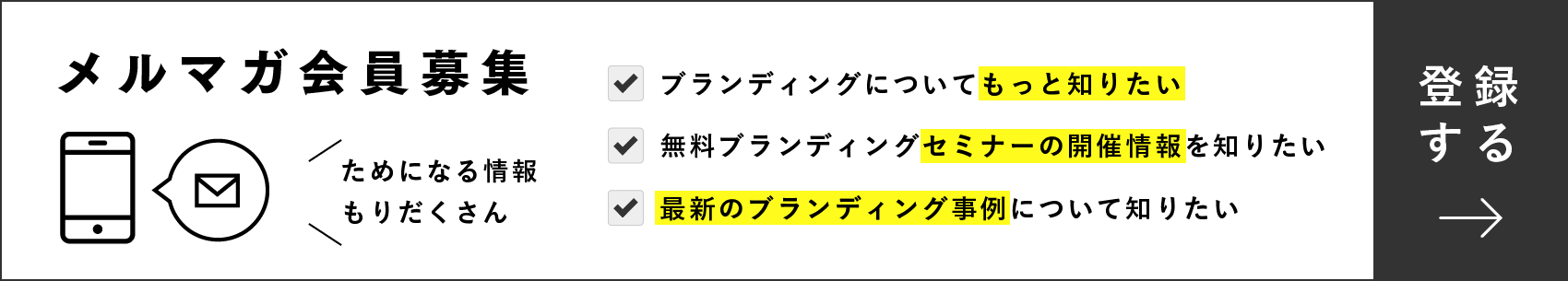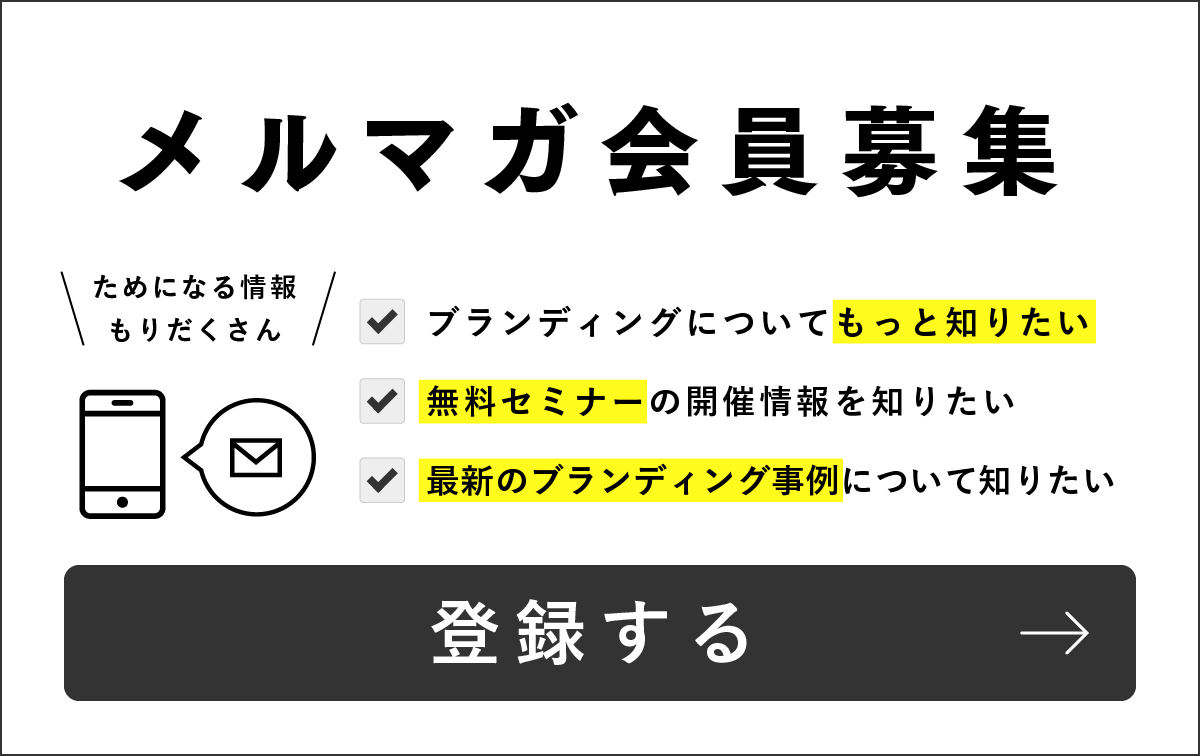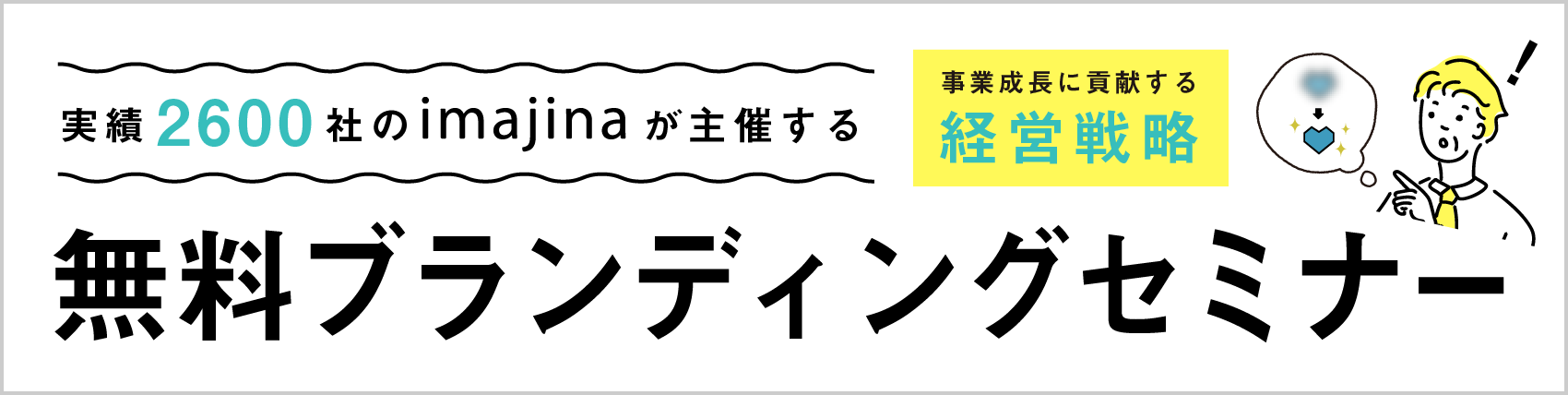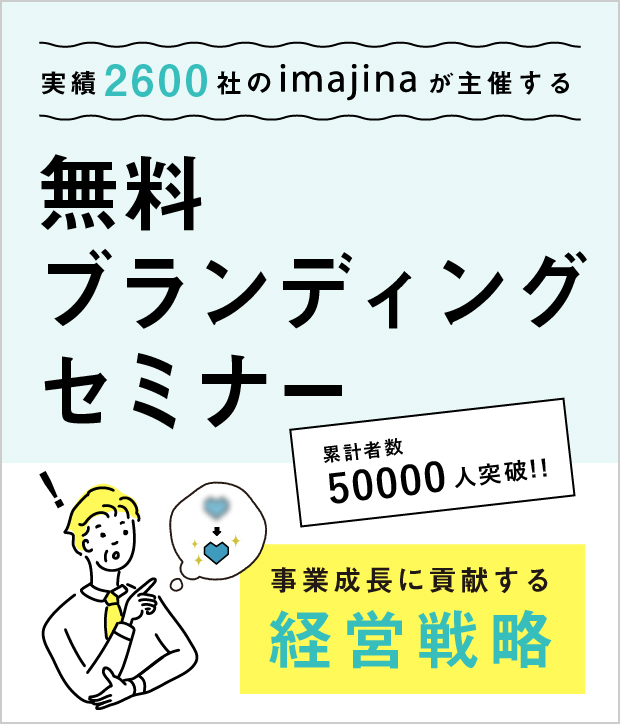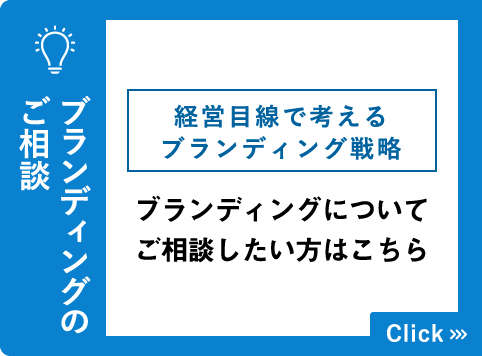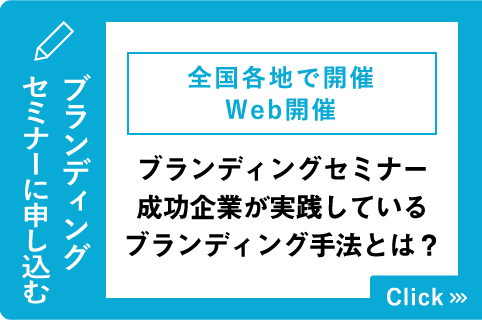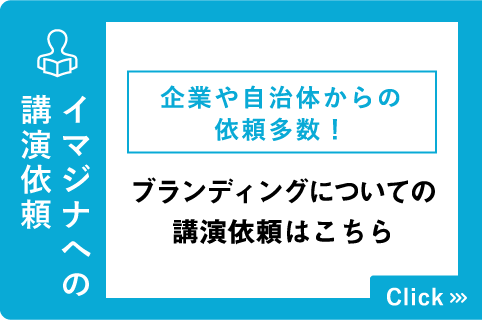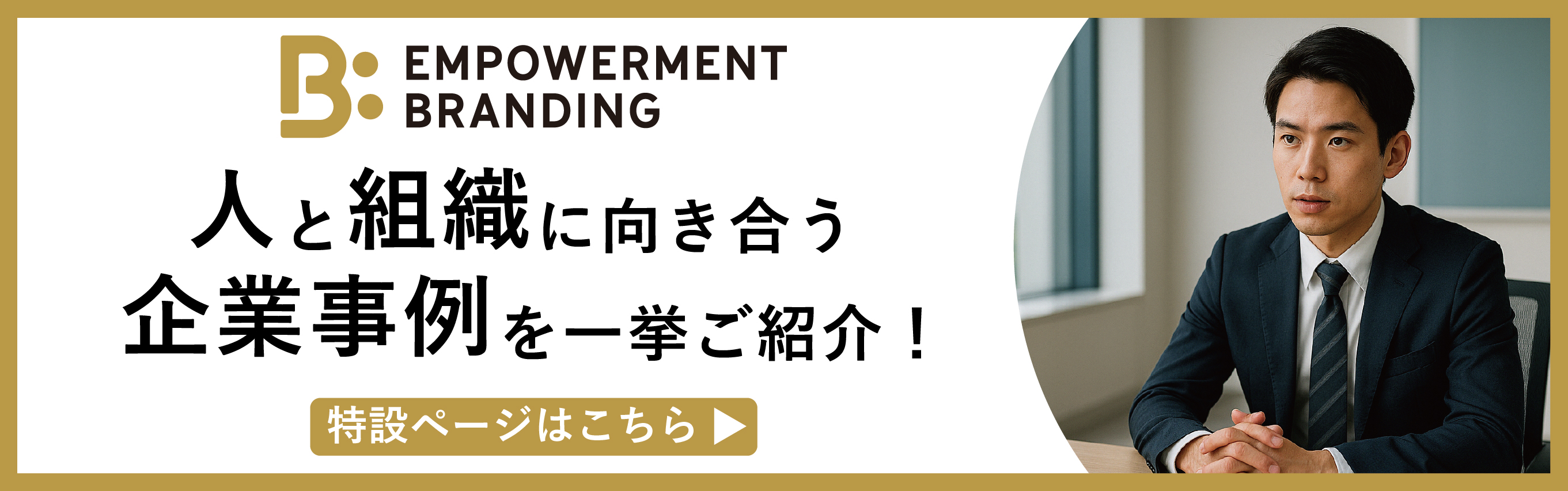たとえ同じ学校に通って、同じ参考書を与えられて、同じ先生から教わっていても、成績に大きな差が出てくるのは一体なぜなのでしょうか?
その違いをつくっているのは、「メタ認知」かもしれません。
メタ認知とは、「自分が思考していることをもう一人の自分がより高次から客観的に捉え、把握する」ことです。
東京大学×ベネッセが共同で2万人以上の小学生~高校生を追跡した調査では、「自分が何を理解していないか確かめながら勉強している」生徒ほど成績がよい、という結果が出ています。

この勉強方法は、「テストで間違えた問題をやり直す」といったその他の勉強方法よりも多くの成績優秀者が実践しているやり方でした。
反対に、「くり返し書いて覚える」といった勉強方法に関しては、むしろ多くの生徒を成績低下に導いていることもわかっています。
ではなぜメタ認知に優れている生徒ほど好成績を残すのか。
謎を解き明かす鍵は、「危機感」にあるのではないかと考えられます。
自分が何を理解していないかを確かめることは、「自分はこんなにも足りていない」という気付きにつながります。
自分に何が足りないかを客観的に精査しない人には、いつまでも「これはまずい、もっとやらなければ」という感覚が起こらないため、当然勉強のモチベーションも上がらないでしょう。
ここまでで見てきたのは高校生の例ですが、このような人間の性質はどんな世代の人にもいえます。
常に現状を客観視し、
「このままではお客様を満足させられない」
「これでは営業目標を達成できない」
そう考えてより良い方法を考え続ける人こそが仕事で成功するというのは、自明ではないでしょうか。
しかし、そもそもメタ認知が得意ではない人や、自らの至らない点に目を向けようとしない人がいることも事実です。
そのような人たちに対し、いかにして「危機感」への気付きを与え、「もっと学ぼう」と思わせることができるのか?
そんな、決して簡単ではない、しかし組織にとって必要不可欠なマネジメントのヒントを、全国で開催の経営・ブランディングセミナーでご紹介します。