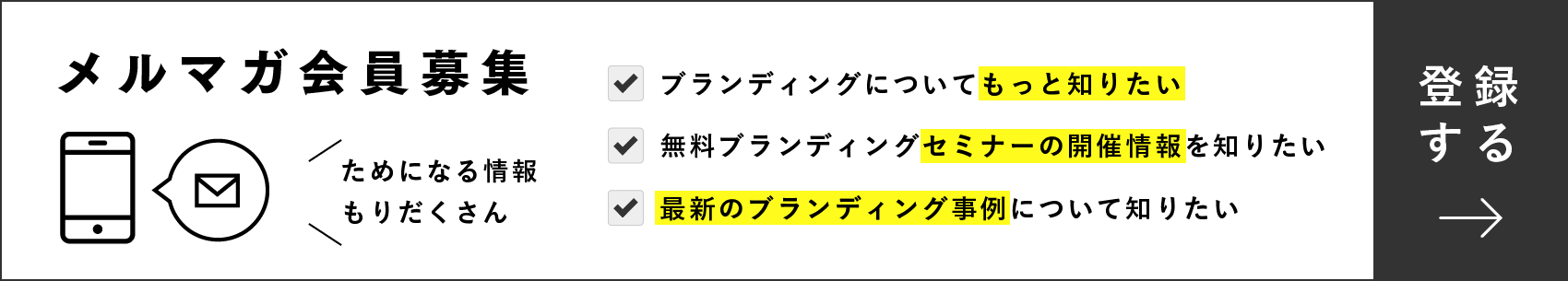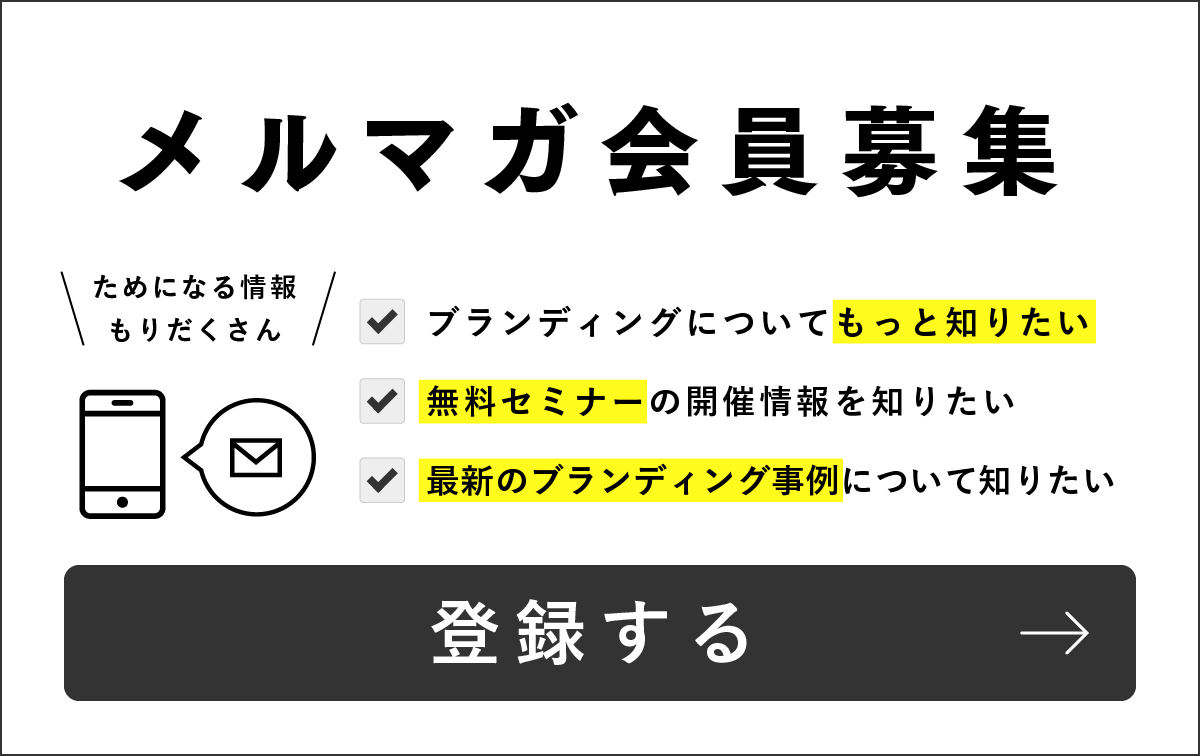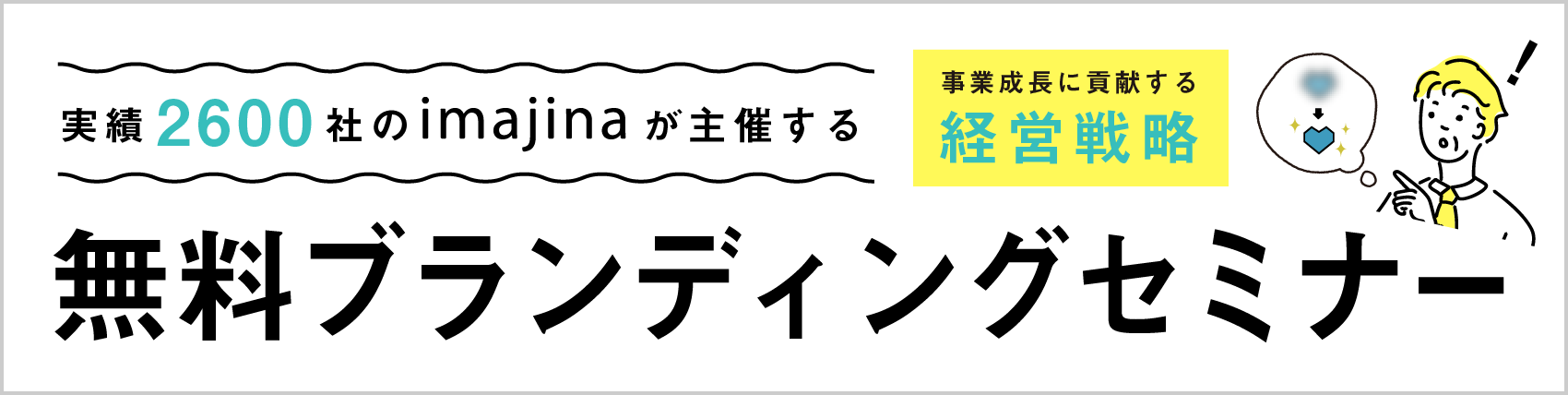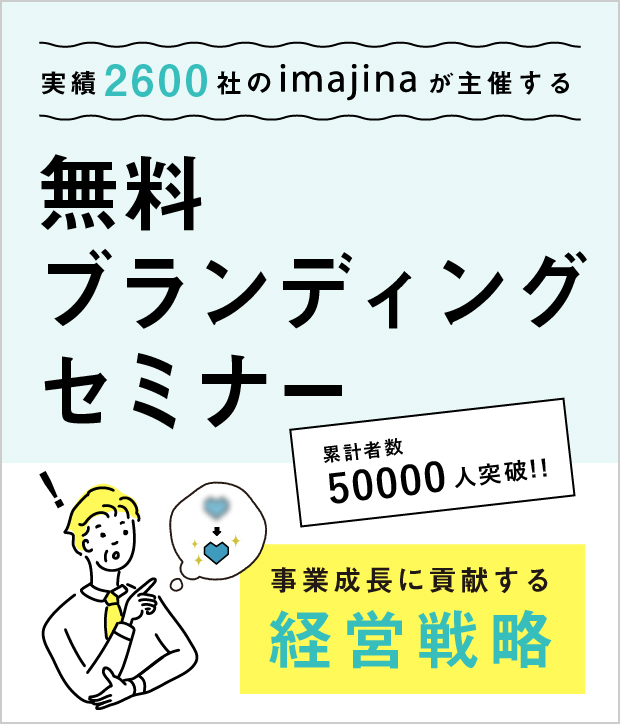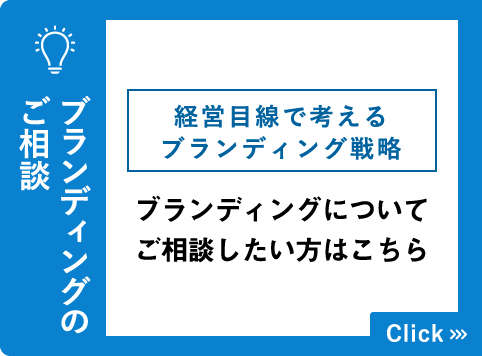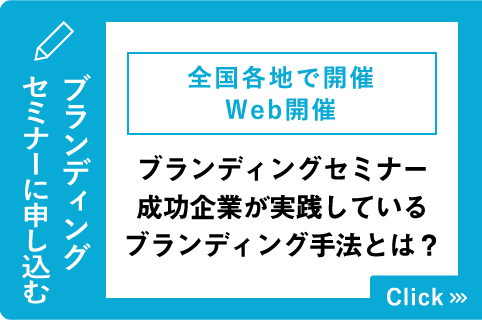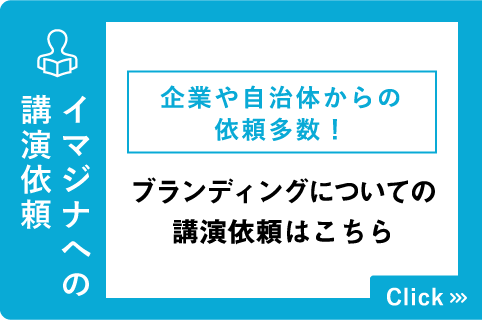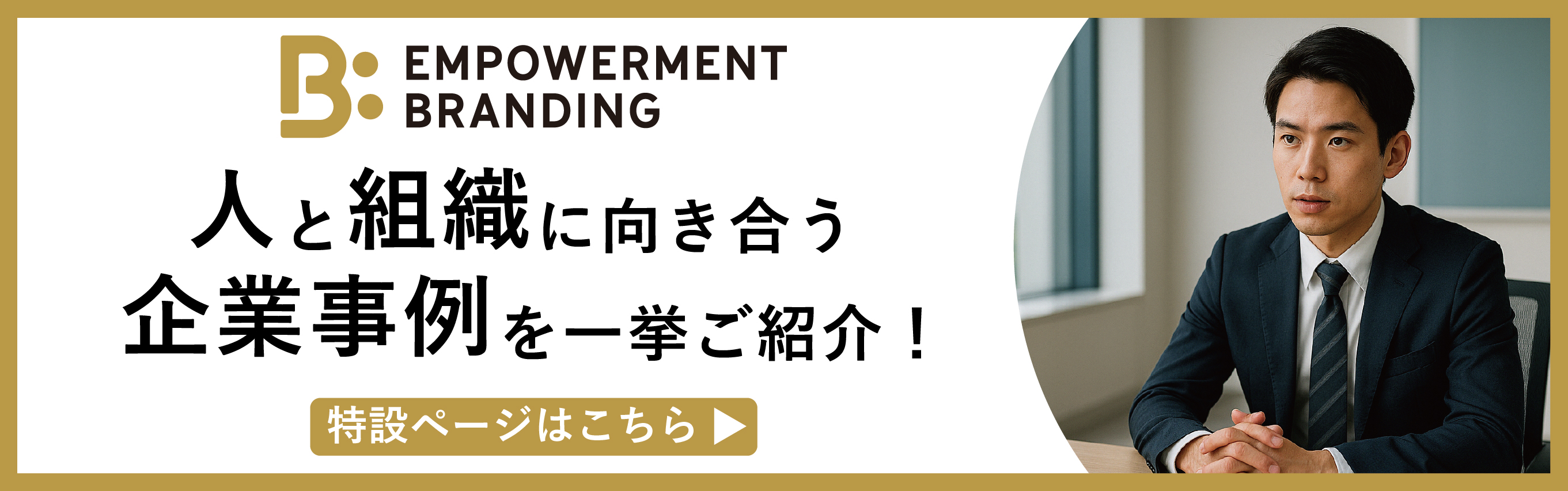「克己心」
自分自身に打ち克つ心。近い言葉としては自制心・セルフコントロールが挙げられます。
座右の銘に掲げる方も多い言葉です。
その重要性について、行動科学で最も有名なテスト「マシュマロ・テスト」から紐解いていきましょう。
マシュマロ・テストはスタンフォード大学の心理学者、ウォルター・ミシェルが1960年代後半から1970年代前半にかけて実施した実験で、その結果をおよそ40年に渡り追跡したものです。
4歳の子どもに対し机の上にマシュマロ1個を置き、15分我慢できればもう1個あげると言って部屋に1人にした結果、我慢できるかどうかを確かめるものなのですが、我慢してもう1個のマシュマロを手にした子どもは約30%でした。
ウォルター・ミシェルはこの時の子どもたちに対し何度も追跡調査を重ねていき、幼少期の自制心と成長後の社会的な成功度の間に相関関係があることを発表しました。
マシュマロを食べなかった子どもたちは、食べてしまった子どもたちと比べて周囲からより優秀と評価され、大学進学適性試験(SAT)の点数も高く、青年期の社会的・認知的機能の評価が高かったのです。この傾向は中年期以降も続き、被験者の大脳を撮影した結果、集中力に関係するとされる腹側線条体と前頭前皮質の活発度において、重要な差異が認められることが分かりました。
克己心の重要性を裏付ける、重要な研究と言えるでしょう。
さらに、すぐに成果が出るようなテーマではなく、何十年にも及ぶ気の遠くなるような追跡調査でようやく結果に結びつくこのような研究を支えたものこそまさに、心理学者ウォルター・ミシェル本人の「克己心」だと言えるのではないでしょうか。
一方、最近の再現実験でニューヨーク大学のタイラー・ワッツらによって示された見解では、マシュマロ・テストの結果は限定的であると発表されています。
彼らの研究は、社会経済的地位を考慮に入れた場合、自制心と将来の生活の質や成功との間にある相関関係が弱まるため、将来の生活の質や成功を決定づけるのは自制心だけではないことを示唆しています。
もちろん、ワッツらが行ったこの研究は、自制心が子どもの将来の生活の質や成功に影響を与える一因であることを否定するものではありません。しかし、子どもの行動や将来の成果に影響を与える要因は多岐にわたり、自制心だけでなく社会経済的背景も重要な役割を果たすということを強調しています。
人はキャッチーで分かりやすい結果や言葉に飛びつきやすい生き物です。
自制心が重要となれば、我慢強ささえ教えればよいと短絡的に結びつけがちです。
なぜなら、その方が楽だからです。
しかし、人の育成はそんなに単純なものではありません。
楽な方向へ流されず、課題に正面から向き合うこと、それもまた「克己心」なのではないでしょうか。