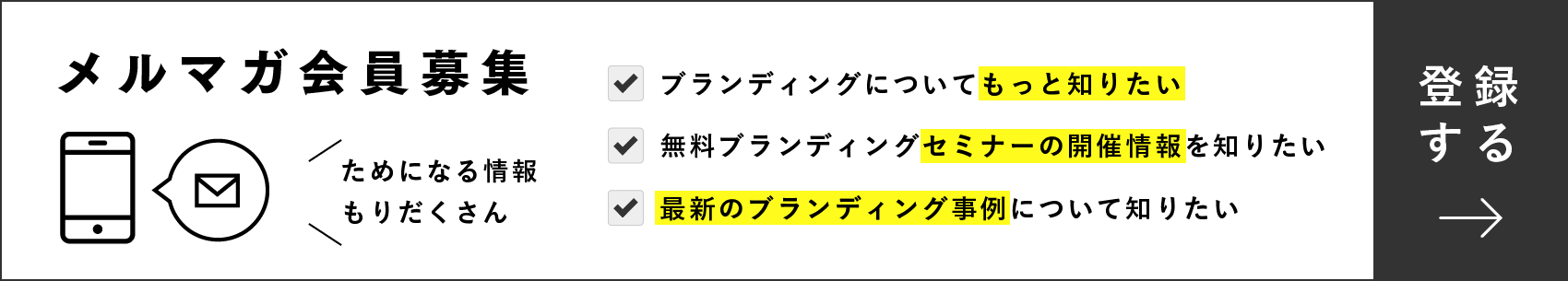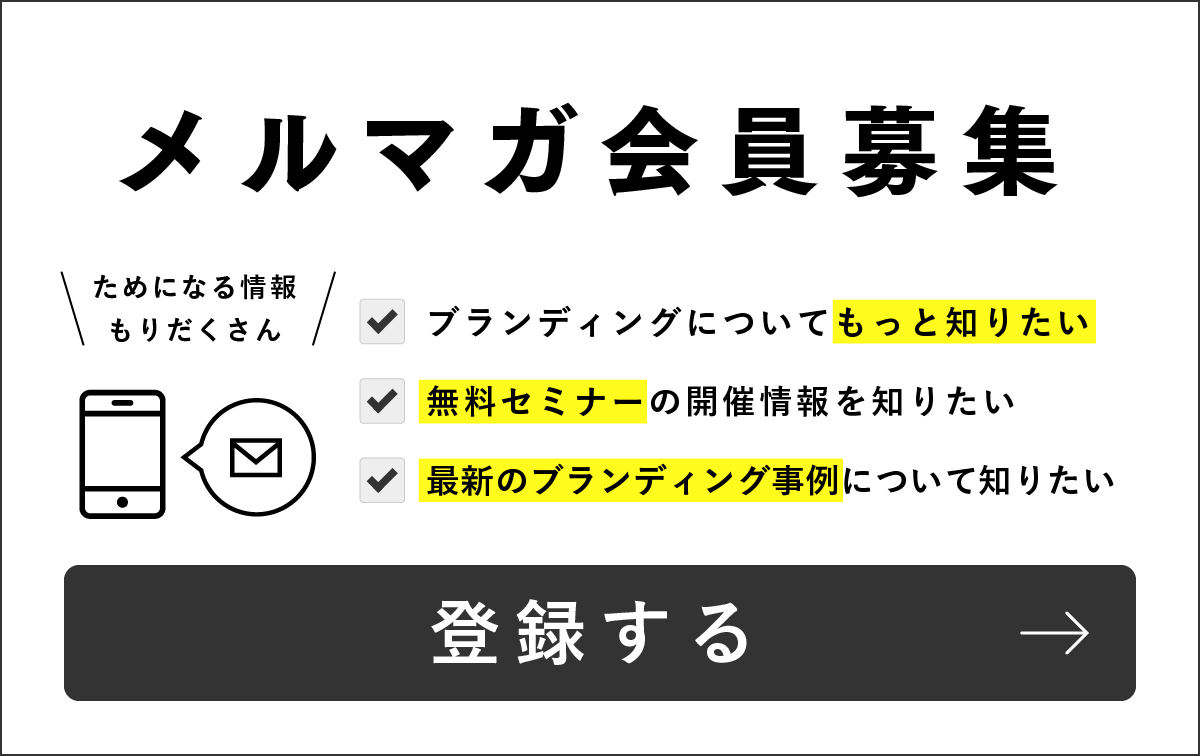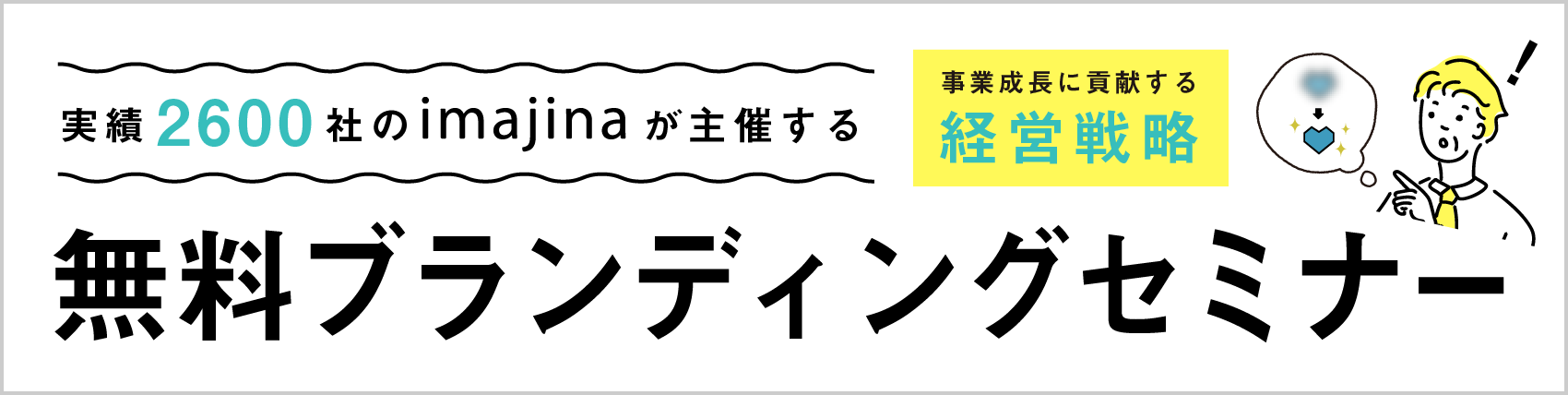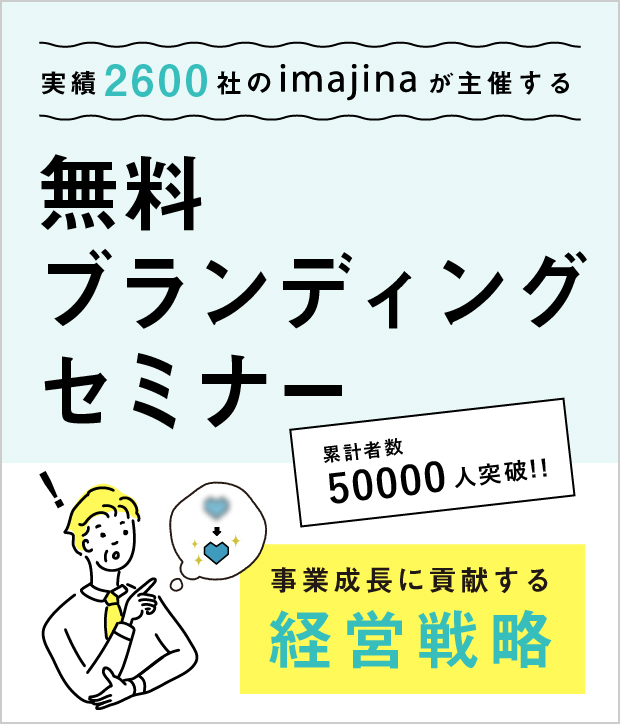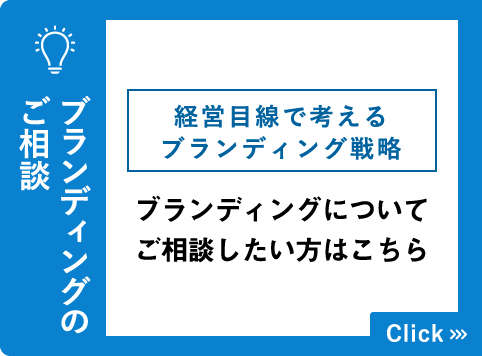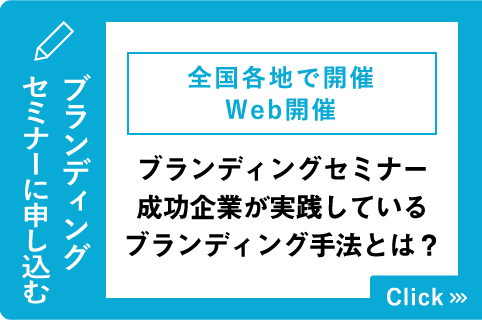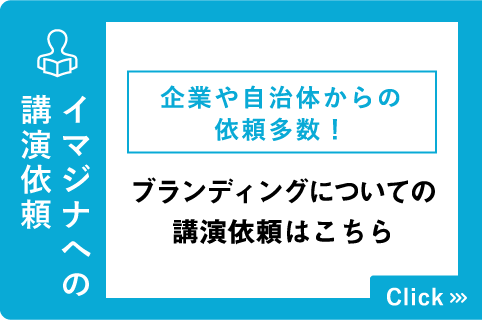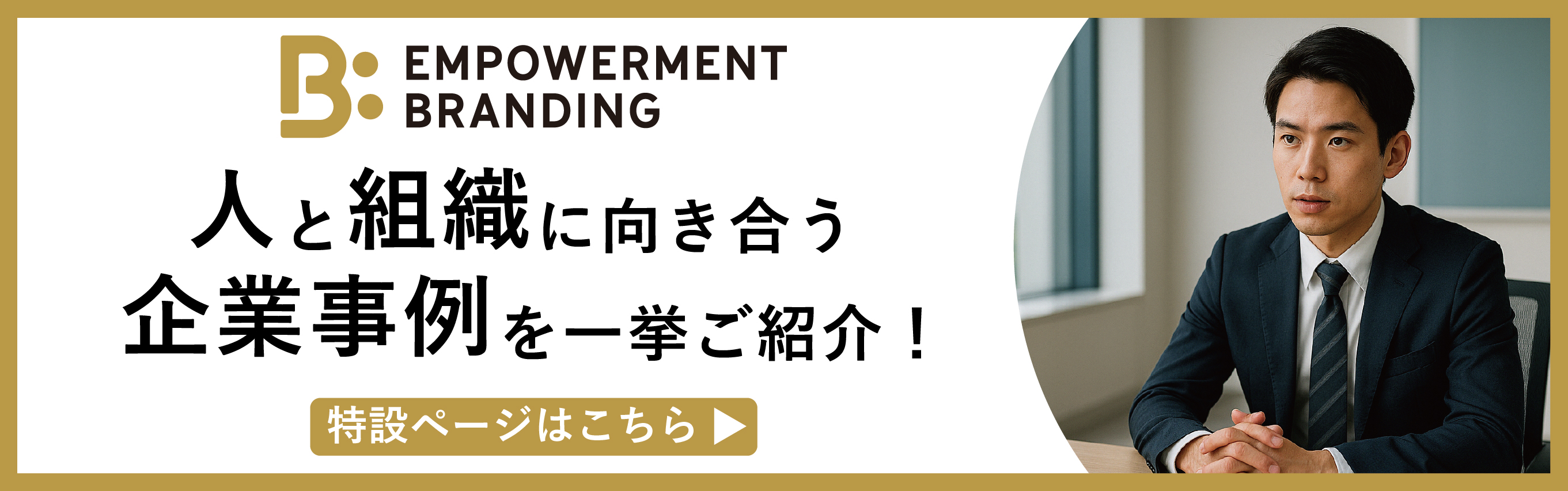「阿吽の呼吸」「空気を読む」「暗黙の了解」という言葉に代表されるように、日本人のコミュニケーションは、言外の意味を汲み取る力、行間を読む力が求められる「ハイコンテクスト」な傾向が非常に強いと言えます。
お互いの共通認識や文化的背景、知識、価値観などの「前提条件」が揃っていれば、すべてを明確に、厳密に言葉で表現しなければ伝わらない「ローコンテクスト」な国よりも質が高く効率的なコミュニケーションが可能でしょう。
しかし、外国人材の流入はもとより、同じ日本人でも世代の違いによる共通認識等の前提条件の崩壊によって、ハイコンテクストなコミュニケーションは極めて限定的なコミュニティでしか成り立ち難いものとなりました。
こういった状況を踏まえ、日本企業がコミュニケーションの質を向上させるために、2つのアプローチが考えられます。
一つは、ローコンテクストなコミュニケーションに合わせるということ。
二つ目は、前提条件を合わせることでハイコンテクストなコミュニケーションを維持するということです。
「前提を揃える文化」への依存が生む弊害とは?
多くの日本企業がこの二つ目のアプローチに手を出しているように感じます。
そのことを示しているのが、「無駄な会議」や「会議への無駄な参加者」の多さです。

「パーソル総合研究所・中原淳 長時間労働に関する実態調査」より
関係者の「前提条件」が揃っていないため、共有すべき情報が増え、会議の時間や回数も増加しているのです。
更に、少しでも関係している社員は皆会議に招集し、そこで何が話し合われたか、参加者の雰囲気、空気感を共有しようとすることで、影響範囲が大きくなります。
残念ながらこのアプローチには少々無理があるように思えます。文脈や空気を読み、阿吽の呼吸で動けることを前提としたハイコンテクストな働きを社員に求めるには、必要な情報があまりにも多すぎるのです。
なおかつ、必要な情報はどんどん変化し続けます。VUCAと言われる時代において、ハイコンテクストなコミュニケーションのみに頼ることは危険だと言わざるを得ません。
とは言え、ローコンテクストなコミュニケーションでも、必要な情報を全て伝えないといけないのだから、結局コミュニケーションにかける時間は変わらないのではないか、と思われるかもしれません。
この点については、ローコンテクストなコミュニケーション文化を持つ国の成功事例を見てみるとよいでしょう。いかにシンプルに、明確に、スピーディにコミュニケーションをとっているかが分かります。
例えばAmazonでは、大半の会議向けの資料は1ページに収めて作る「ワンページャー」という決まりがあります。
読み手によって解釈がブレるため、図やグラフ、箇条書きを禁止しており、文章で表現することが求められます。
また、新規事業の提案資料はプレスリリース形式で作成する決まりとなっています。
こうすることで「行間を読む」必要がなくなり、「いつでも」「誰でも」「正しく分かる」ようになるというわけです。
会議においても、冒頭5分間は全員でワンページャーを黙読する時間が設けられており、全体像や自分が意思決定すべき箇所、すべき質問を確認した上で議論が始まります。最短距離でゴールに向かう仕掛けがされているのです。
会議の参加人数も、意思決定に関係する4~8人と決められており、日本の大企業のように何十人もが会議室に並ぶようなことはありません。
Amazonの事例が他の企業でも有効とは限りませんが、ヒントとすることは可能でしょう。
会議だけではなく、日常の部下から上司への報告や、上司から部下への指示にも転用ができるかも知れません。
日本人の文脈や空気を読む力を活かしつつ、文化、性別、世代を超えた最も効率的なコミュニケーションの仕方を各企業が作り上げていく必要があります。
そしてこのような企業文化に関わることは、現場からアイデアが出てくることもありますが、本来は経営者が実行しなければなりません。
Amazonのワンページャーも、CEOのジェフ・ベゾスの指示によるものです。