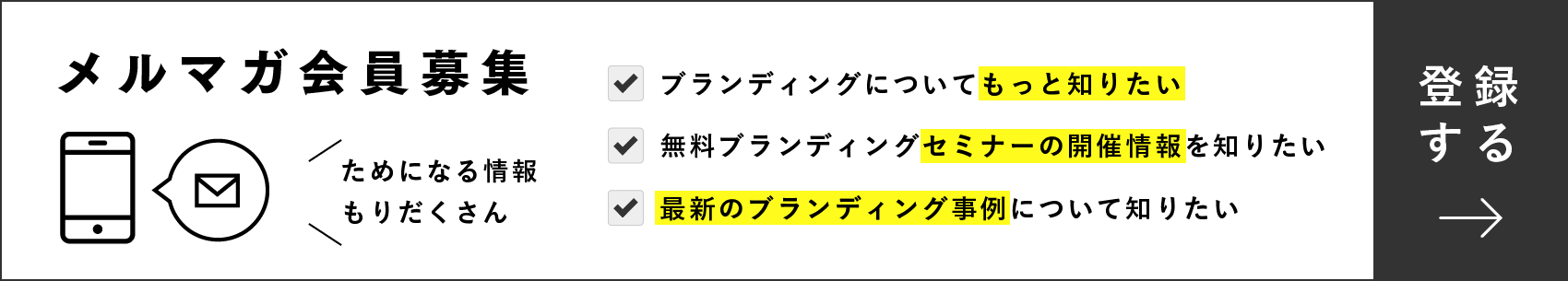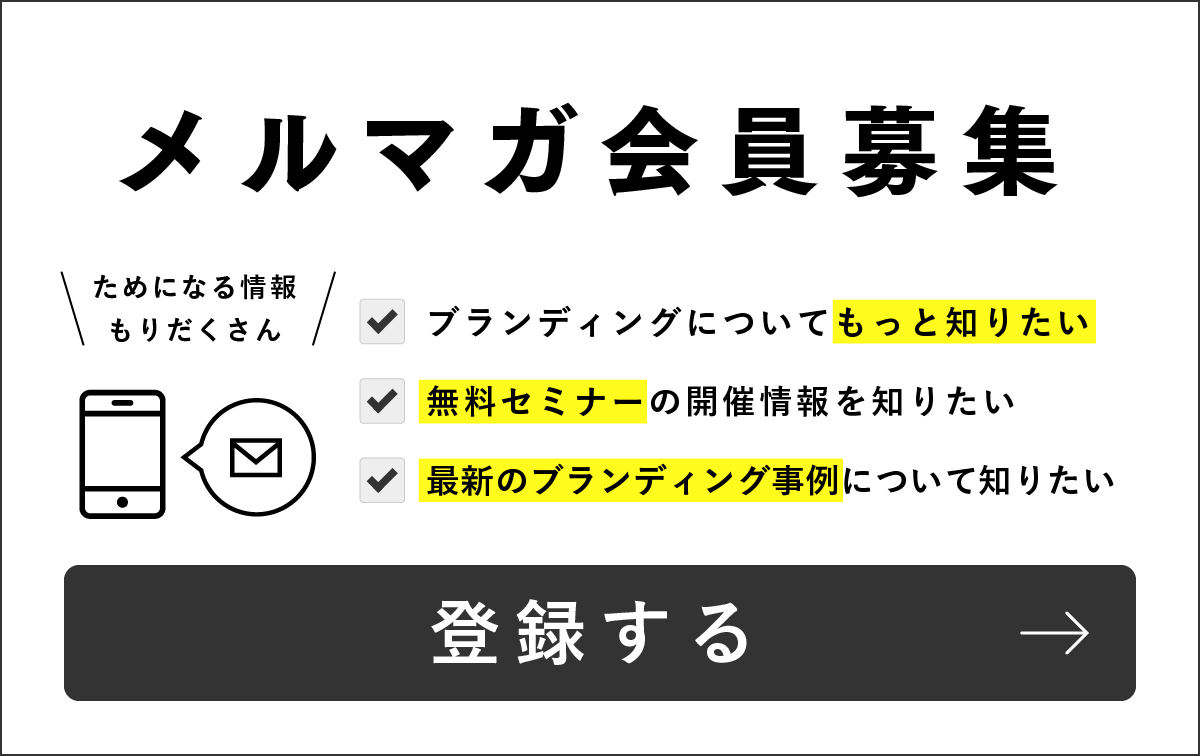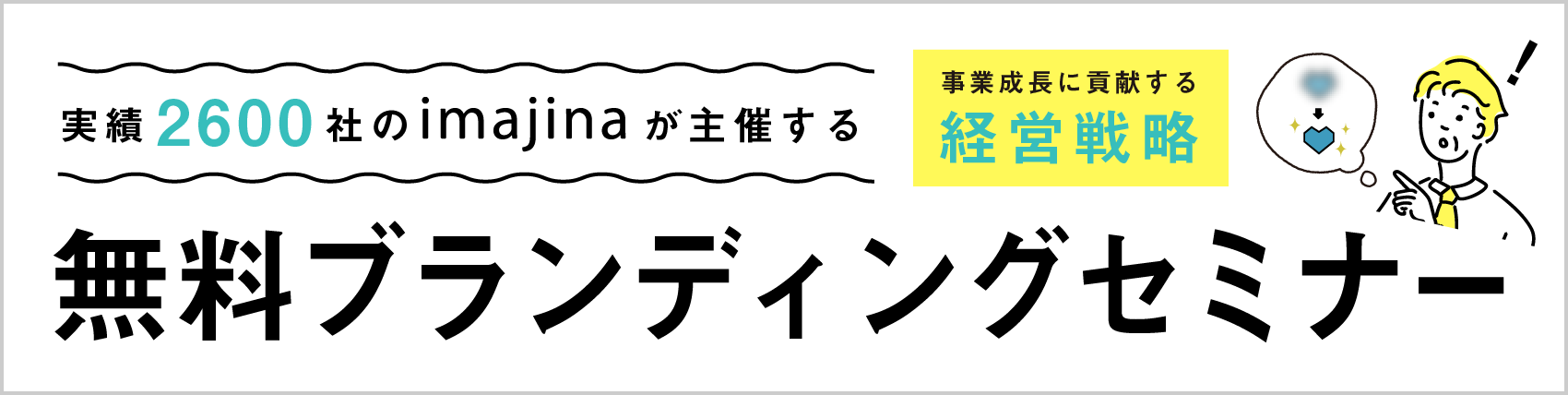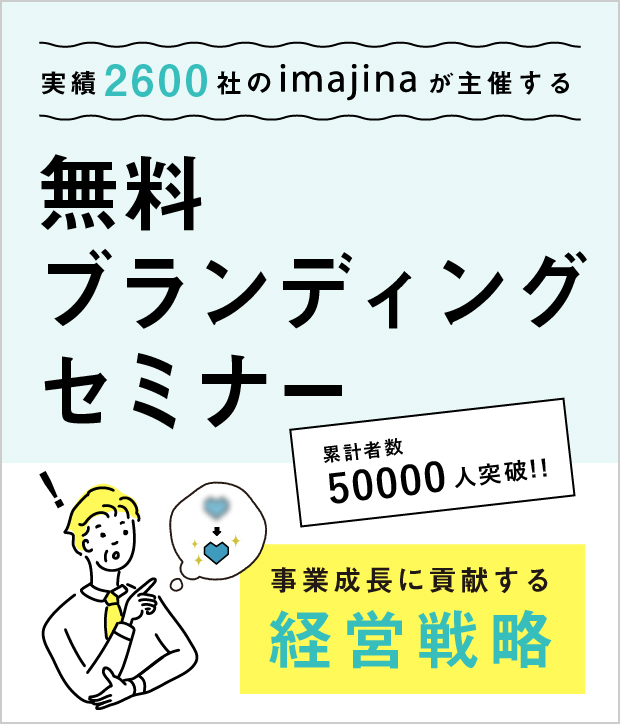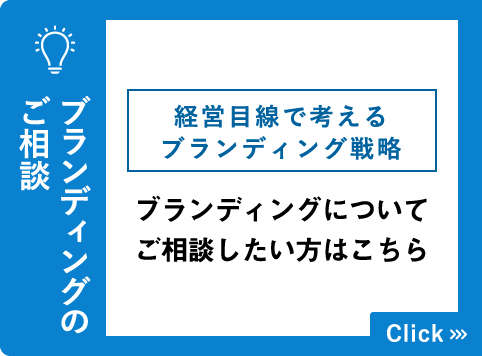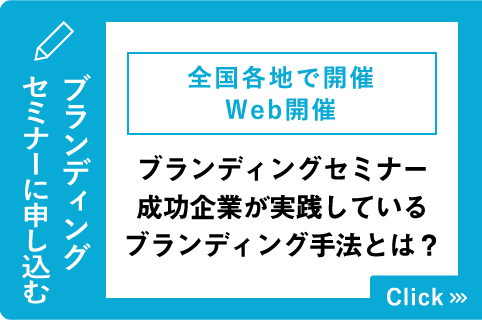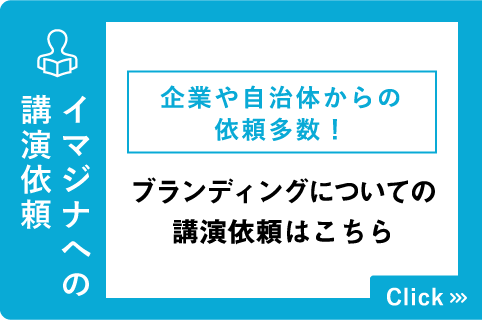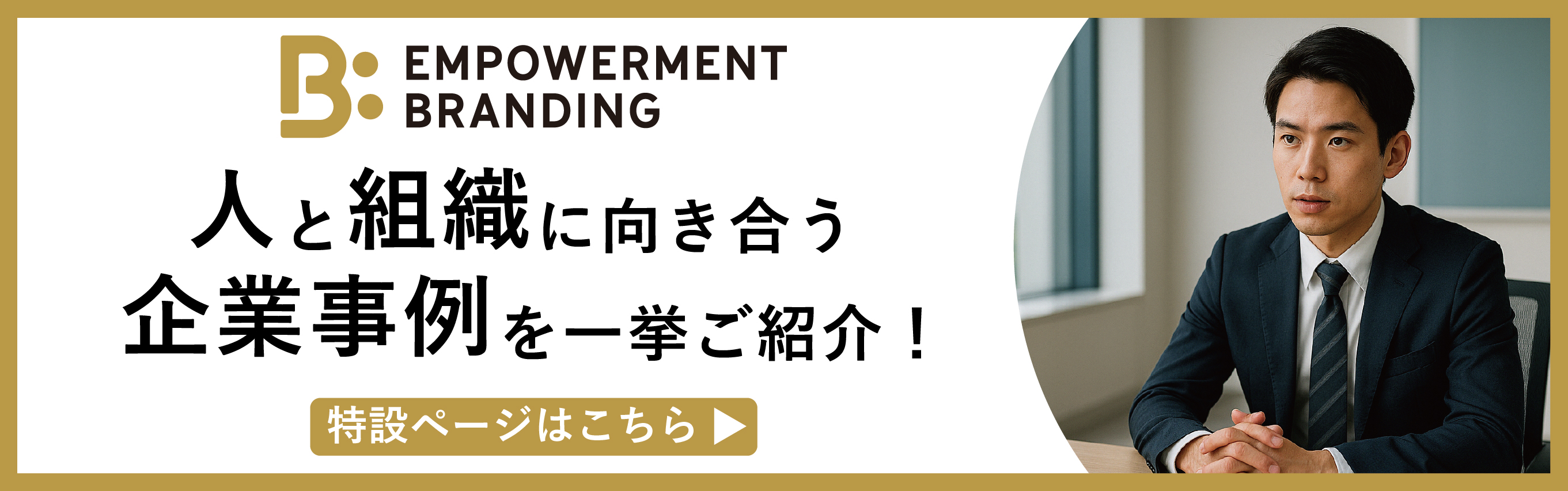表題のような議論は、様々な研究機関や知見者によってなされています。
もちろん、組織成長においてはどちらの存在も非常に重要であり、社内の人員をどちらか一方に偏らせる必要はないかもしれません。
様々な説が存在する中で、まず一つの研究データを見てみましょう。
アメリカのシンクタンクの調査によると、批判的思考力やコンピュータースキルなどのより高度な分析スキルが求められる職につく人は、1980年から比較して83%増加していることがわかっています。
ロボットやAIの台頭により、単調な作業がどんどん取って代わられていることは皆さんもご存知の通りでしょう。
この時代に必要とされる人材であり続けるためには、自分の強みを探り、専門性を高めていくことが重要であるといえます。
専門性が求められる時代、日本人の意識は?
一方で、別の世界的な調査では、日本人が専門性を軽視しているということがわかっています。
「自分の仕事に専門的なトレーニングが必要か」を尋ねたところ、世界平均では53%が強い同意を示しているのに対し、日本では31%にとどまりました。

専門性が必要不可欠になっていく世界の流れがあるにも関わらず、日本にはスキルアップに対する危機感がない人が多すぎるといえます。
さらに、日本の若者世代に目を向けてみましょう。
大学生を対象としたリクルートの調査では、「その企業においてこそ役立つスキル」よりも「どこの会社に行ってもある程度通用するような汎用的なスキル」を身に着けたいと考えている人が圧倒的に多いことがわかっています。
つまり、日本の若者はゼネラリスト志向といえます。

この傾向は、転職が当たり前になっている社会の風潮とも深く関係しています。
一社で働き続けるかどうかわからないからこそ、その会社で求められる仕事にのめり込みすぎるのではなく、広い知識を身に着けたがるのです。
しかし、「その会社で役に立つスキル」を極めることは、果たして「その会社以外では活躍できない」こととイコールでしょうか?
むしろ、「その会社の方針に沿って自分の力を伸ばし、貢献する」ほどまでに目の前の仕事と会社に向き合っているならば、会社や周りの人からの信頼も厚く、意欲と成果に対しても高い評価を受ける人材となっている可能性が高いでしょう。
そもそも、「その会社でしか使えないようなスキルだけが身に着く仕事」などない、ということもいえます。
例えば、営業一本で努力を積んだ場合、製品知識といった会社に固有の知識ももちろん高まりますが、信頼を勝ち取るようなコミュニケーション力や顧客のニーズを敏感に察知する力など、それこそ「どこでどんな仕事に携わる場合にも重宝する力」も同時に伸びるものなのです。
個人のスキルは、ドリルの穴と一緒です。
何かの知識を追求しようと深く掘り進めれば、穴の直径は広がっていきます。
つまり、自分の武器を尖らせようとすれば、それに付随しておのずと様々な能力がついてくるものなのです!
若い時間は有限。
もっとも人が成長するその時期に、
「どこに行ってもそこそこできる」を目指して、いろんな分野に手を出すのか?
「まずは目の前の仕事を極める」と腹を括り、5年後10年後にはそれだけでも食っていけるようなスキルを身に着けている、そんな状態を目指すのか?
その選択が、本人の人生を左右します。
もし皆さんが若手の方と向き合う中で、「なぜ目の前のやるべきことに集中せずに、二兎を追うようなことをするんだ」と思われることがあったら、こんな時代だからこそ、ぜひ一つのスキルを掘り下げる意味やメリットを丁寧に伝えていただきたいと願っています。
若手が自分の強みに向き合い、武器を身に着けていく。
それがそのまま組織の成長につながります。
企業成長を実現するための「経営・ブランディングセミナー」、只今申込み受け付け中です。