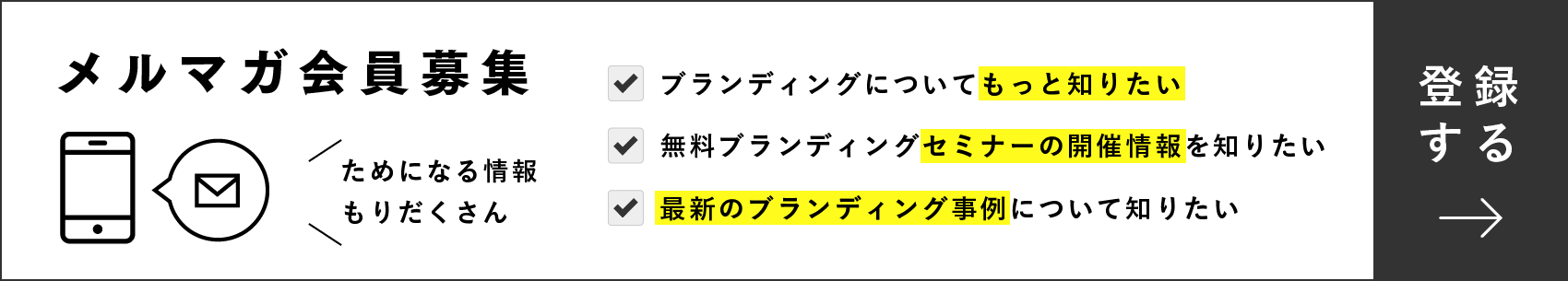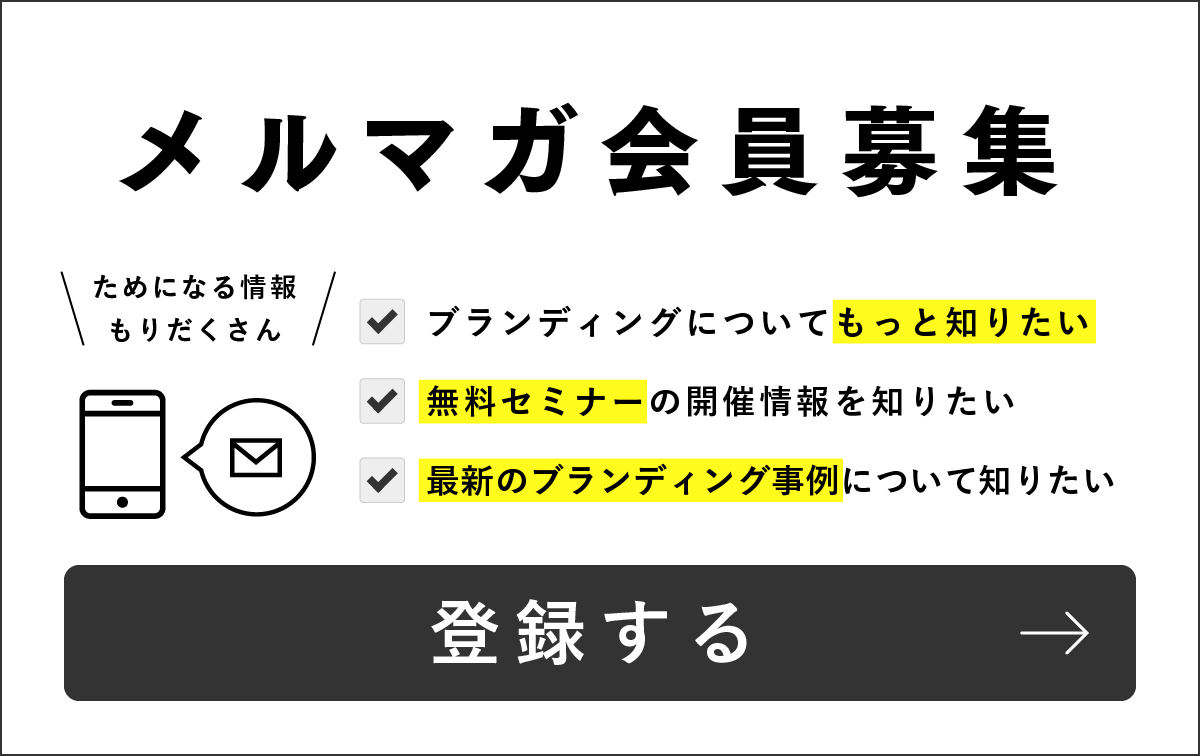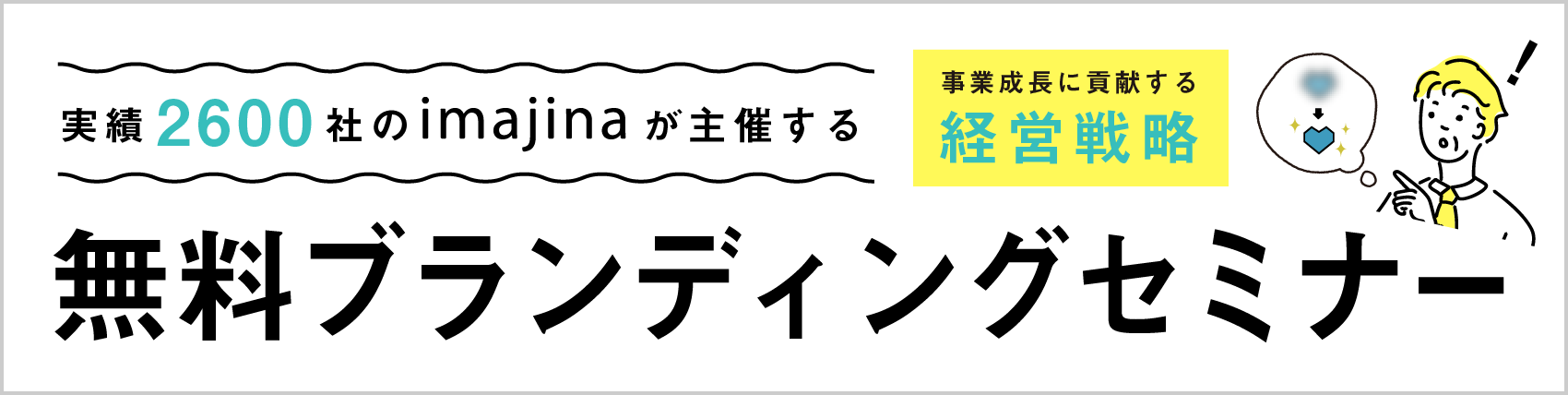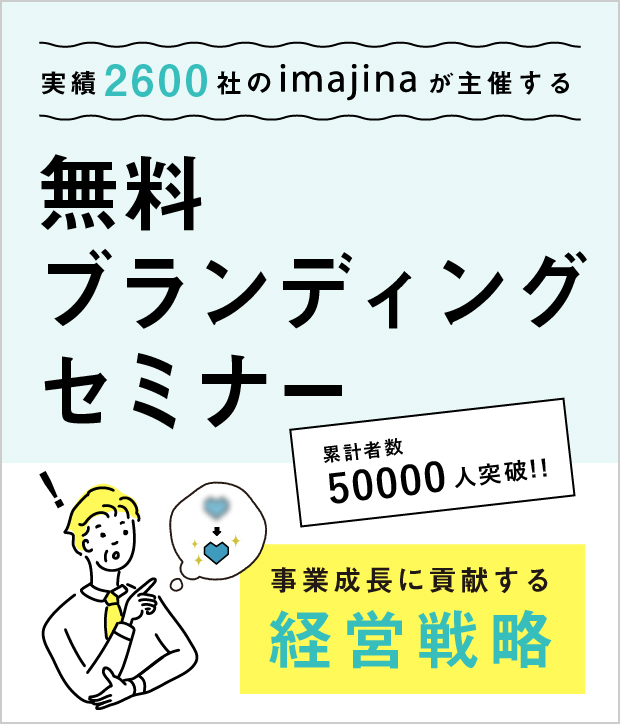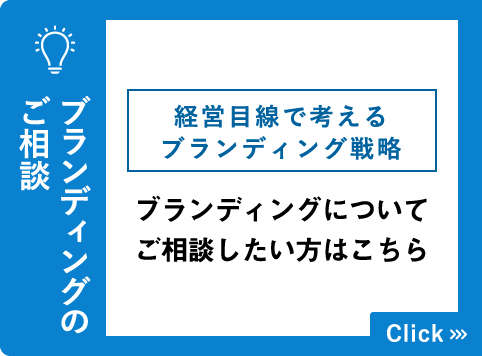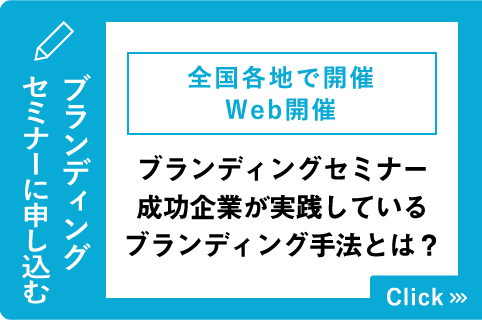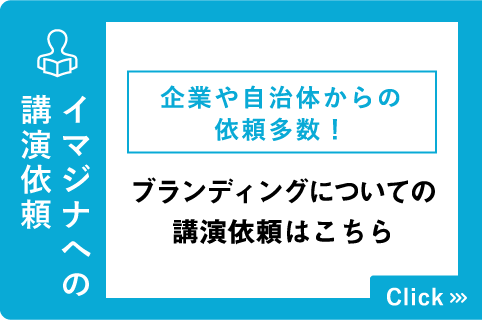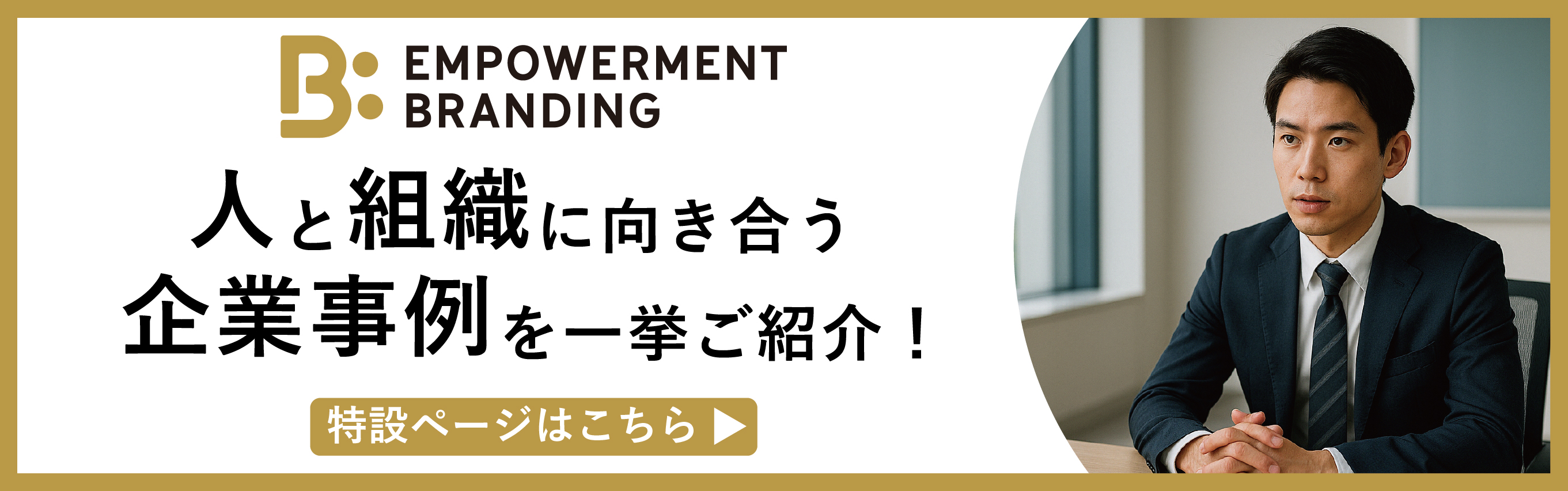皆さんのPCにはメール・チャット・オンライン会議といったコミュニケーションツールはいくつ入っていますか?そして、その対応に業務時間のどれくらいを毎日費やしていますか?
パンデミックをきっかけにこのようなツールは定着し、より便利で効率的に、リアルタイムで(それこそ国境も越えて)の共有が当たり前となってきました。
しかしそれは、働く人のコミュニケーションがこのようなデジタルツールを介して「常時オン」の状態にいるということでもあります。
通知のたまったチャットや何十人も入ったCCメールが毎日メールボックスに一定量届いている中で、自分にとって重要なメールを探し当てるのに一苦労といった経験をされた方は多いのではないでしょうか。
Microsoftの2021年に発表されたレポートでは、多くの人が1週間の勤務時間のうち85%以上をメールやインスタントメッセージ、電話、ビデオ通話に費やしているとしています。1日8時間労働で週5勤務とした場合、40時間のうち実に34時間以上にあたります。
コミュニケーションの氾濫ともいうべき状況は時に、情報の混乱、コミュニケーションロスによる生産性の低下や、対応疲れによる社員の燃え尽き症候群に繋がりかねないとされています。
「伝えたつもり」で終わらせない、背景と全体観の共有
ここでお伝えしたいのは増えてしまったコミュニケーションを減らせばいいということではありません。情報が溢れる中で、いかに適切で生産的なコミュニケーションをとるかが重要ということです。
例えば、チャットで「〇〇をお願いします」と一言で依頼をするのと、少しだけ顔を見て経緯や背景と併せて依頼をするのでは、どちらが望んだ結果を得やすいでしょうか?
連携が不十分の場合、依頼を受けた人は自ら情報を探すことから始めなければなりません。2018 年の IDC 調査では、 「データを扱うプロフェッショナルが毎週 30%をデータの検索・管理・準備に、20% を重複した作業に費やしている」としています。
確かに、対面で丁寧に説明するときと比べて、一言のメッセージで依頼するときの方がコミュニケーションコストは少ないかもしれません。しかし、結果として意図したものと違うアウトプットが来た場合に、それを確認・指摘・修正して再チェック…となればその分の時間と作業の損失のほうが大きくなってしまうのです。
だからこそ、コミュニケーションをとるときには「背景・全体観」といったものを目的に添えて伝えることでビジョンを共有することが重要だと考えています。
弊社の管理職研修の中でもこのフレームワークは受講者全員に実施いただいています。全体観・背景についての説明は、職位によって社内で回ってくる情報量の違いや視座の違いを埋める役割を持っています。
実際の研修でも、「自分は全体観を把握していると思っていたけど、実はずれていた…」「全体観を共有できている人とは話の速さが違う」といったコメントが寄せられています。
ぜひ、「背景・全体観を伝える」を会話の中で試してみてはいかがでしょうか?