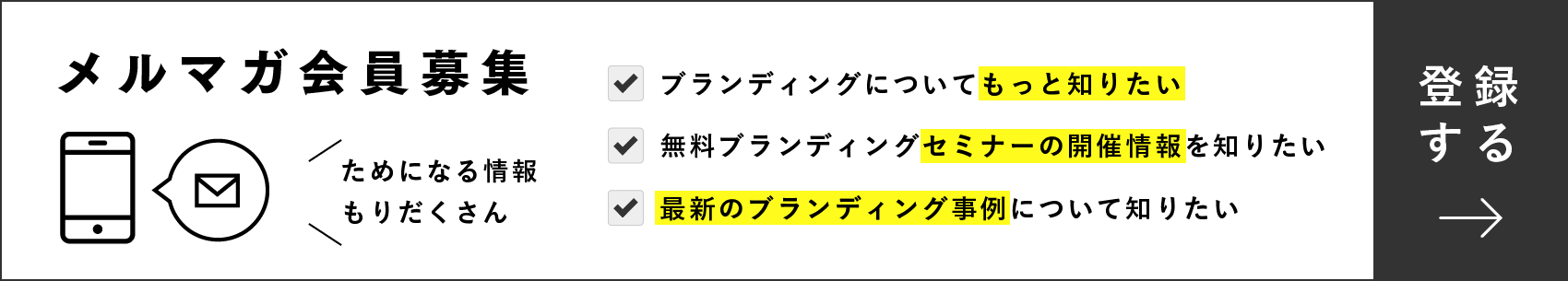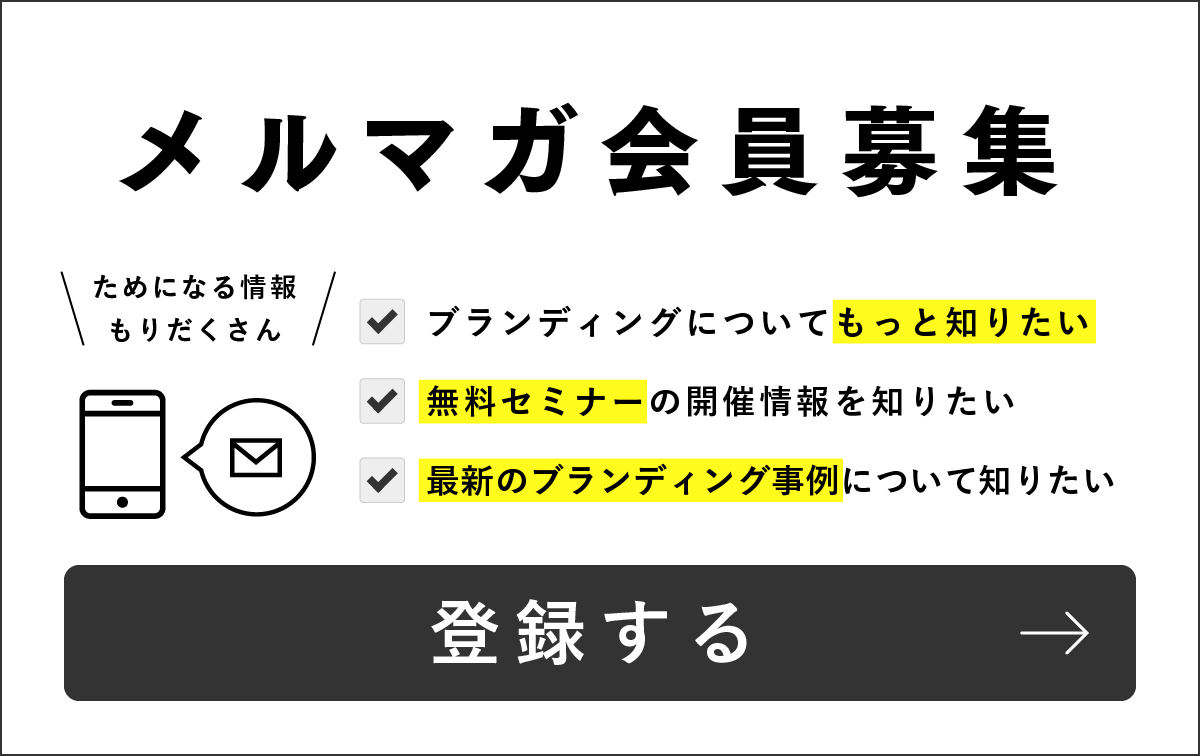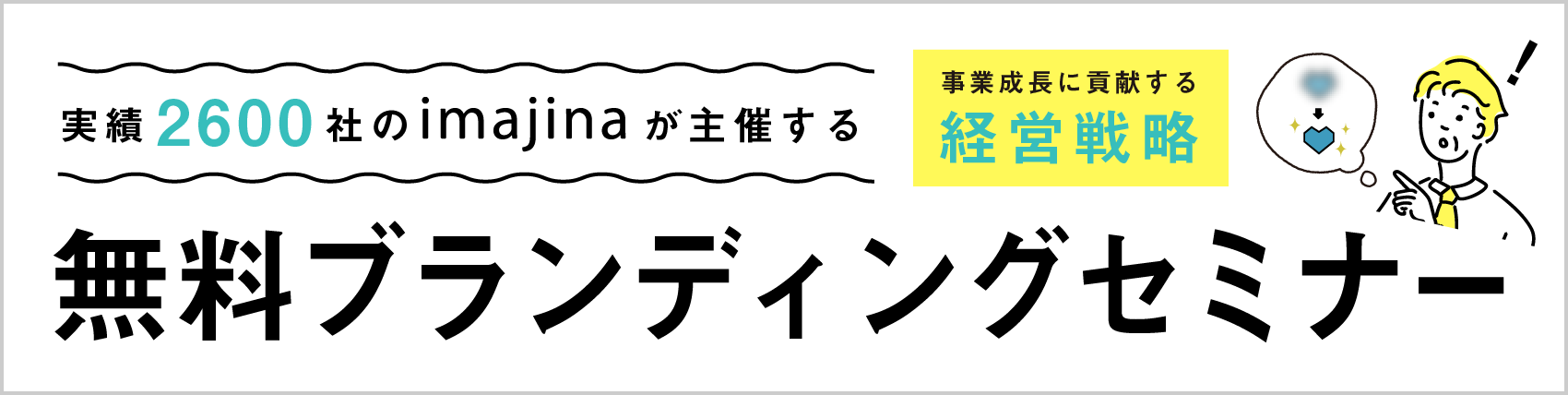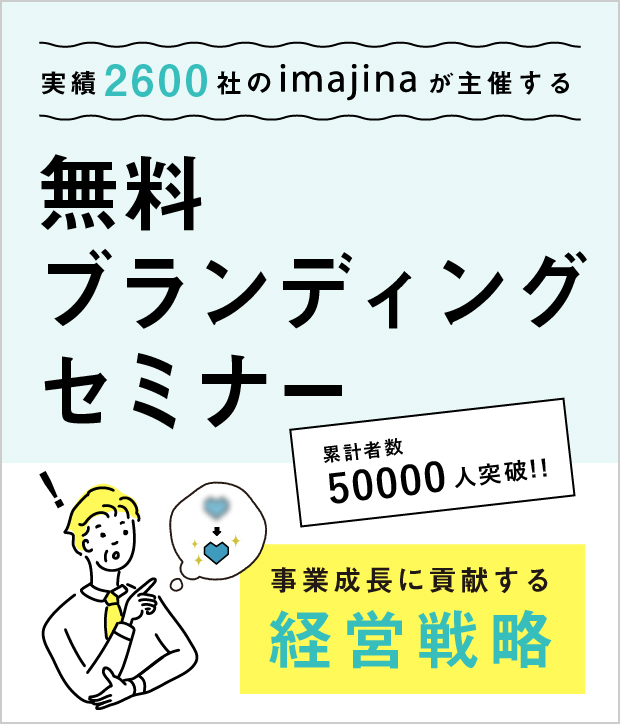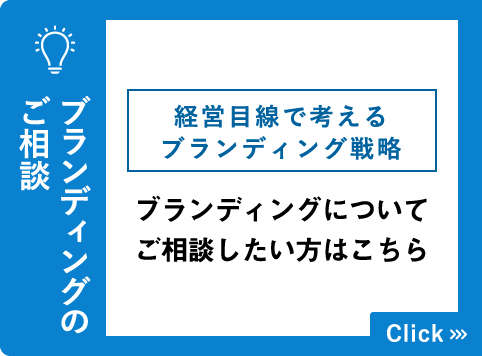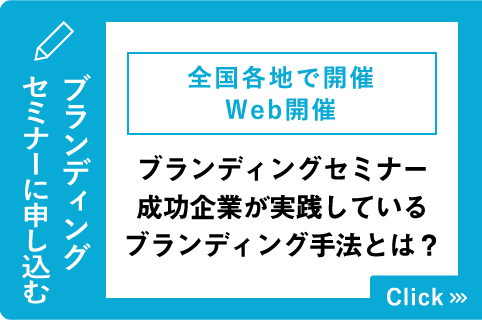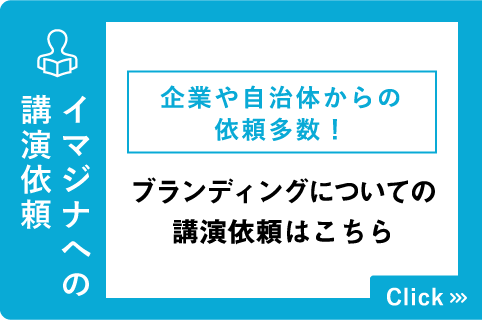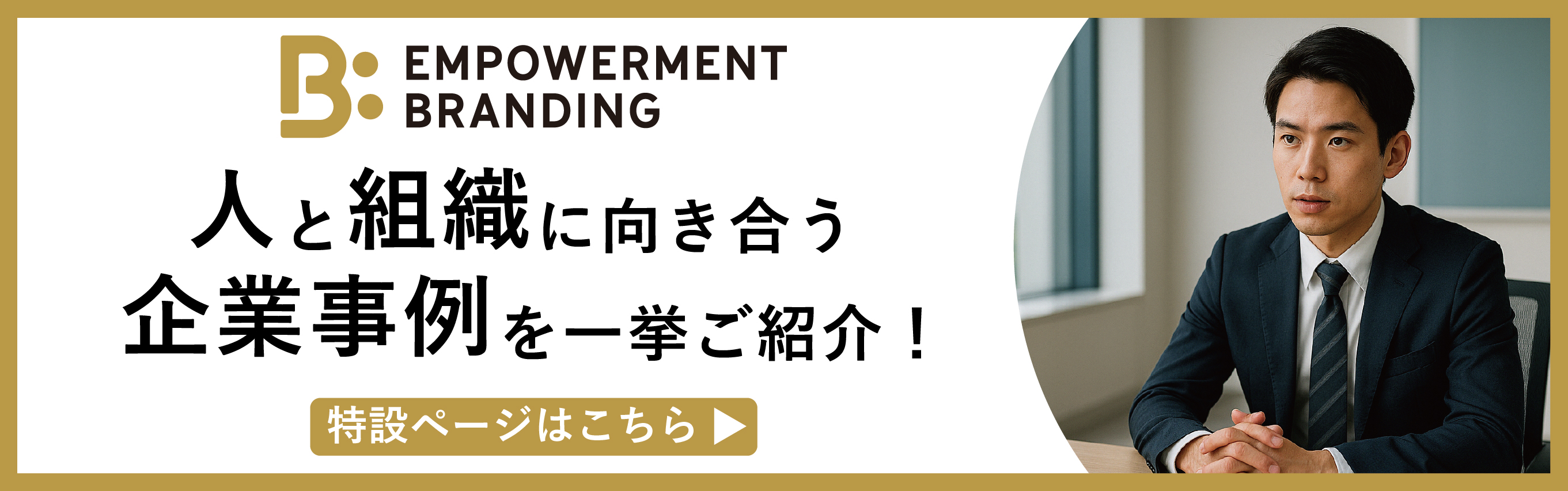以前、部下の目標設定において、「成功が動機になる人」と「失敗回避が動機になる人」で同じ成功率に対して異なるモチベーションが働くというお話をさせていただきました。
前者は成否の可能性が50/50の時にモチベーションが上がり、後者は逆に成否が決まっている方が腹をくくって行動する傾向にある、というものです。
モチベーションや目標は一人ひとり異なって働くもので、上司はその人の傾向を把握していくことが必要という話でした。
社員が“無理ゲー”をやり遂げる組織とは?
今日は世界で最も有名な無茶ぶり(?)企業の実例をお伝えしようと思います。
先月10日、イーロン・マスク氏は自動運転タクシー「ロボタクシー」構想を発表しました。自動運転どころかハンドルすらない完全自動運転EVを2年以内に3万ドル(約459万円)という破格の値段で販売するという構想です。
投入予定地の一つ、カリフォルニア州に対し、テスラは完全自動運転の認可申請すらしていない段階でのこの発表。もし、あなたがテスラ社員だったらどう受け止めますか?
「最高に面白そうだ!やってやる!」と思う人もいるでしょう。一方で、「申請もしていないのに2年ではムリでは?」と思う人ももちろんいるでしょう。
テスラ社内ではこういった代表の大言壮語ともいえる発表を、社内通知などではなく、SNSの投稿で知ることも多いとのこと。
多くの社員は「次はこれをやるんだな」と知り、ものすごい勢いで組織一丸となって動き出すので、代表に振り回されるような悲壮感のある現場ではないそうです。
(引用:NewsPicks 【働き方】なぜテスラの社員は「無理ゲー」を形にできるのか)
みんなテスラに入社してくる時点で「持続可能なエネルギーへ世界の移行を加速する」というミッションに共感している人ばかりであり、そのミッションをかなえるために必要だと感じたら、文句も出てこないのです。
ここで2つのポイントがあると考えます。
一つはミッションへの絶対的な共感です。会社のミッションを理解し、共感したうえで入社をしている。アップルやグーグルといった各業界でトップ・オブ・トップと言われている会社を渡り歩いてきた優秀な人物がミッションに共感をして入社をしているのです。
そして2つ目は、ミッションをかなえるためには代表の壮大な構想も”必要だ”と感じて動いているという点です。つまり、社員がミッションと次の構想を自分のアクションとして捉えている。みんな10倍の成果を出すためには、10倍働く環境とのこと。(巷で言われるワークライフバランスとは真逆ですね)
もちろん、すべての会社がかくあるべきという話ではありません。お伝えしたいのは、会社・組織の目指す先を社員一人ひとりが理解し、そこに共感することがいかに重要か。そして、それを社員一人ひとりのアクションにつなげるためには社員自身の自分事化が必要である、ということです。
それは会社への信頼ともいえるでしょう。
実際に、信頼とモチベーションは連動しています。ハーバードビジネスレビューでは、信頼性の高い組織の従業員の勤務中の意欲は、信頼性の低い組織の社員に比べて76%も高いと報告されています。
企業の想いと目の前のプロジェクトがどうつながっているのか、どれだけ大切なことなのか、そして、社員一人ひとりが業務として日々携わっていることの全体観をいかに共有できるか、組織への信頼につなげられるかが、変化の激しい現代に求められているのではないでしょうか。
弊社のセミナーでは企業・組織の想いをどう伝えていくのか、実際に企業で実施させていただいた実例や、キーマンとしての管理職へのトレーニング内容などをお伝えしております。