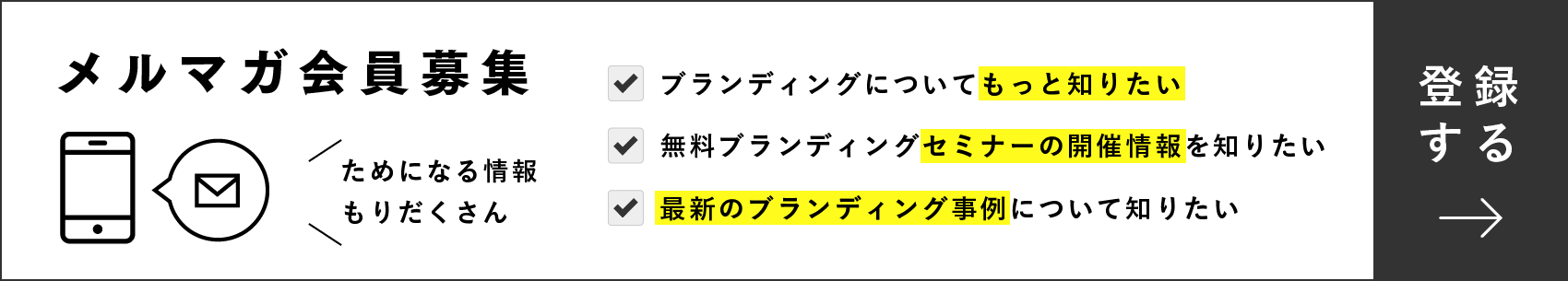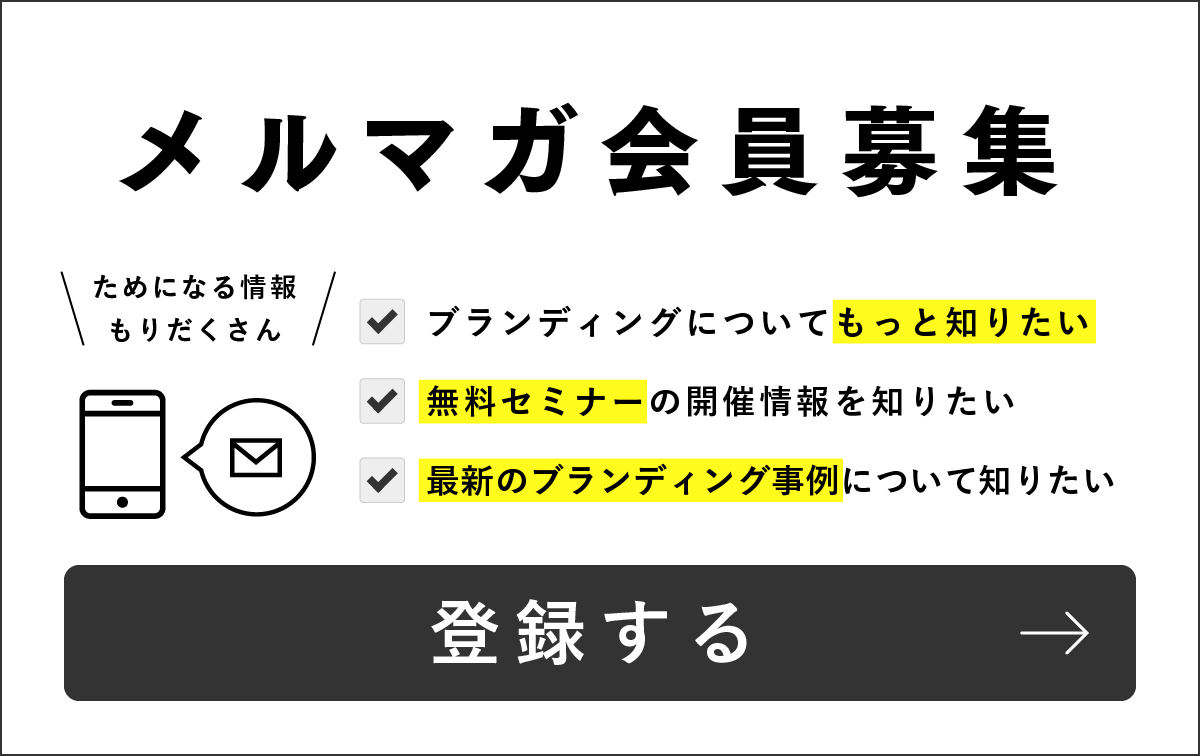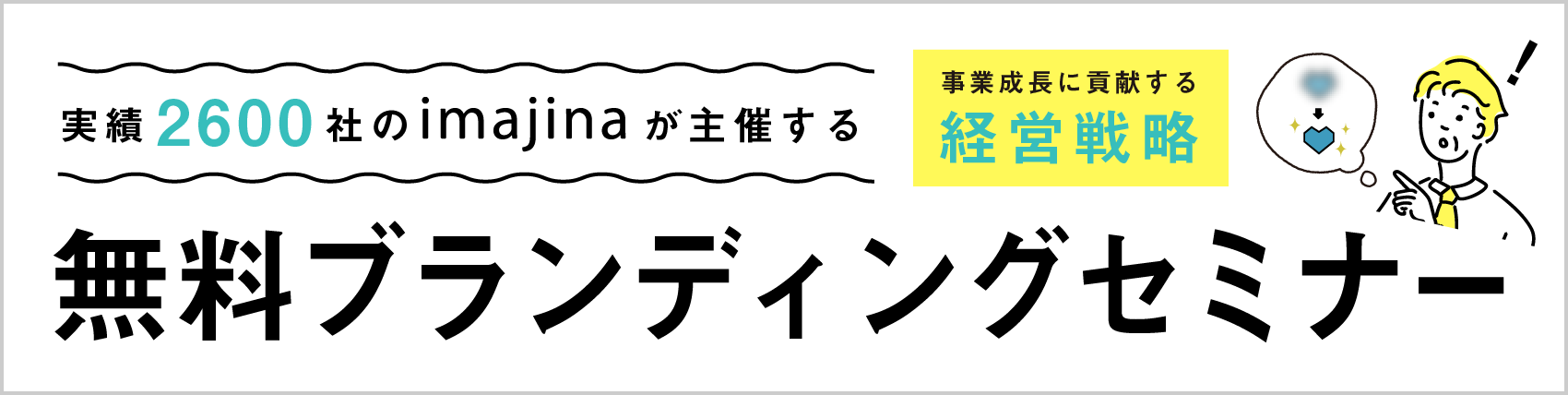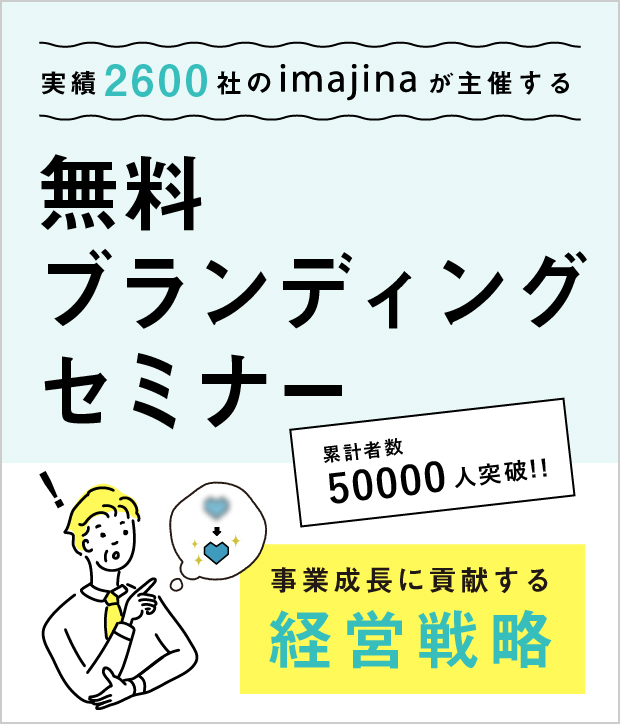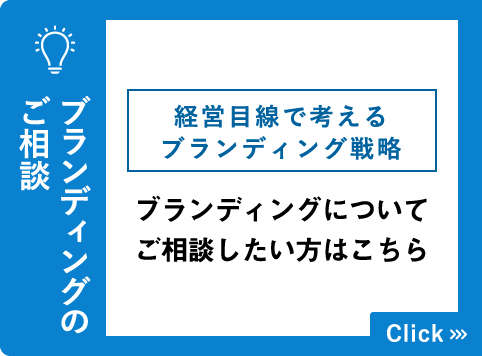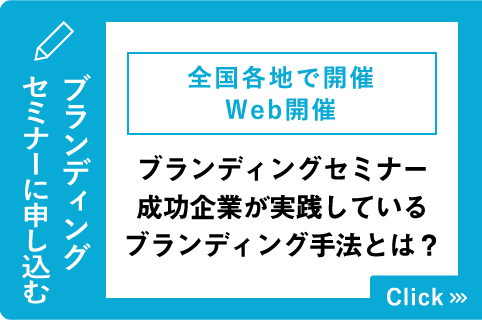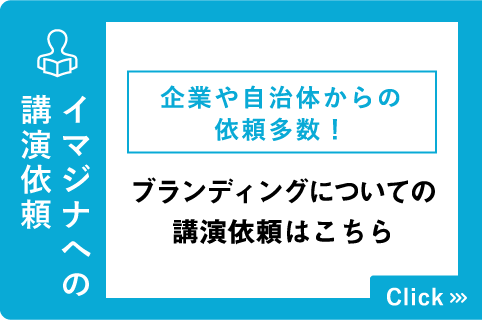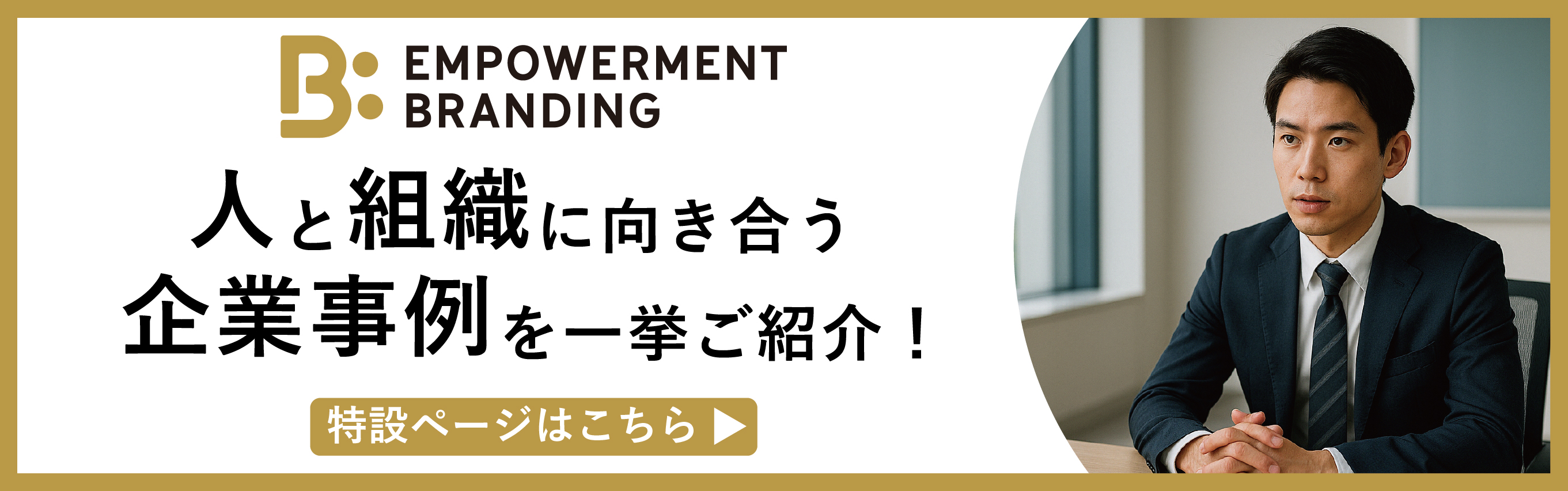人口減少、平均賃金の低迷、進化し続けるAI技術。
変化し続ける現代日本社会において、多くの企業が後継者不足に悩まされています。
会社として業績不振ではないにもかかわらず、後継者の不在により「あきらめ休廃業」を余儀なくされている企業は実に、10社に6社。M&Aの市場もここ30年で15倍の拡大を見せ、平均賃金も2015年に韓国に追い抜かれています。
さらには時価総額の推移も、深刻に受け止めるべき数値を叩き出しています。旧東証1部上場企業 全2169社の時価総額の合計を、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftのたった5社の合計値が上回ったのです。
では、時価総額の高い企業、つまり将来的な成長に期待されている企業は何が違うのでしょうか?
その答えは、「人への投資」にあります。
AIやロボット技術が進化し続け、単純作業が次々と機械に代替されるようになった昨今、私たち人間の価値は「考える力」の上で問われるようになりました。
これからの働く「人間」の武器は、ホスピタリティ、クリエイティビティなど、人だからこそ発揮できる「思考力」。
それを踏まえて、従業員の自ら考える力をどれだけ伸ばせるか、すなわち人材教育にどれだけ投資しているかが、企業の価値を測る基準となったのです。
世界各国の企業が、人、知識などの「無形資産」に投資するようになる中で、日本ではいまだに設備などの有形資産が80%を占めています。
これが、日本と他国の企業における期待値の莫大な格差を生んだ正体です。
これから先の時代を生き残っていくのは、そこで働く人の力を最大限に「活かす」ことができる企業です。
そして、ただ組織の人材を動かすだけでなく「活かす」ためには、部下を導く立場にある「管理職」が非常に重要となってきます。
会社の将来を描いていく上で人的投資が不可欠である以上、全社員が会社の目指す方向性を理解し、そこに共感し、一貫したビジョンを持って働くことが求められます。
しかし、ここでも厳しい現実が立ちはだかります。
多くの企業が頭を抱える、「若手の早期離職」という問題です。離職理由として最も多く挙げられるのが、入社後3年未満の若手の場合は「キャリア成長が望めないから」、入社後3年以上の場合は「会社に将来性がないから」。
貴重な人財として育てていかなければならない若手がなぜ、会社に対してこのような失望を抱いてしまうのでしょうか?
その答えを握るのは、会社の「管理職」です。
働く若手は、上司としての管理職層を日々、意識しています。しかし、現代日本における「管理職になりたくない若者」の割合は実に83%。
つまり、若者たちは日常的に関わる上司の姿を見て「忙しそう」「大変そう」「自分はこうなりたくない」と思い、会社を離れていくのです。
逆に言えば管理職が魅力的であり、企業のショーウィンドウ的な役割を適切に果たせている場合、若手はその姿に感化され、さらなる高みを目指すマインドを持つことができます。
「自分もこの会社で頑張って、この人のようになりたい」という、未来への希望を抱くのです。
会社の将来を見せることは、社員のやりがいを高める上でも非常に大切です。
優秀な人ほど、「このままこの会社で働き続けたら…」と、自身の行く先を考えて次の行動を選択します。
有望な未来がないと判断して転職してしまうといったケースを防ぐには、5年後、10年後、社員ひとりひとりが何を実現できてどのような可能性がひらかれているのかというビジョンを、会社が示し続けなければなりません。
日本の企業の管理職は、世界と比較して圧倒的にマネジメント能力が低いというデータがあります。
実際、企業の94%が管理職の育成に課題を抱えていますが、研修などマネジメントの手法を学べる場所はあまり提供されていません。
しかし、先程も述べたように管理職は企業のショーウィンドウ、モデルケースとなる存在です。
管理職のブランド価値を高める「管理職ブランディング」を徹底することは、社員の定着、人材獲得、生産性向上など、企業全体に何重にもメリットをもたらすのです。