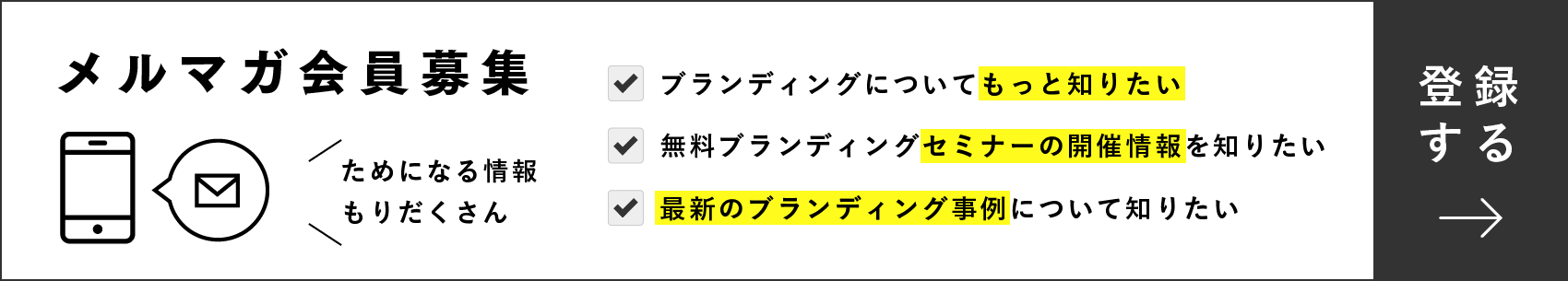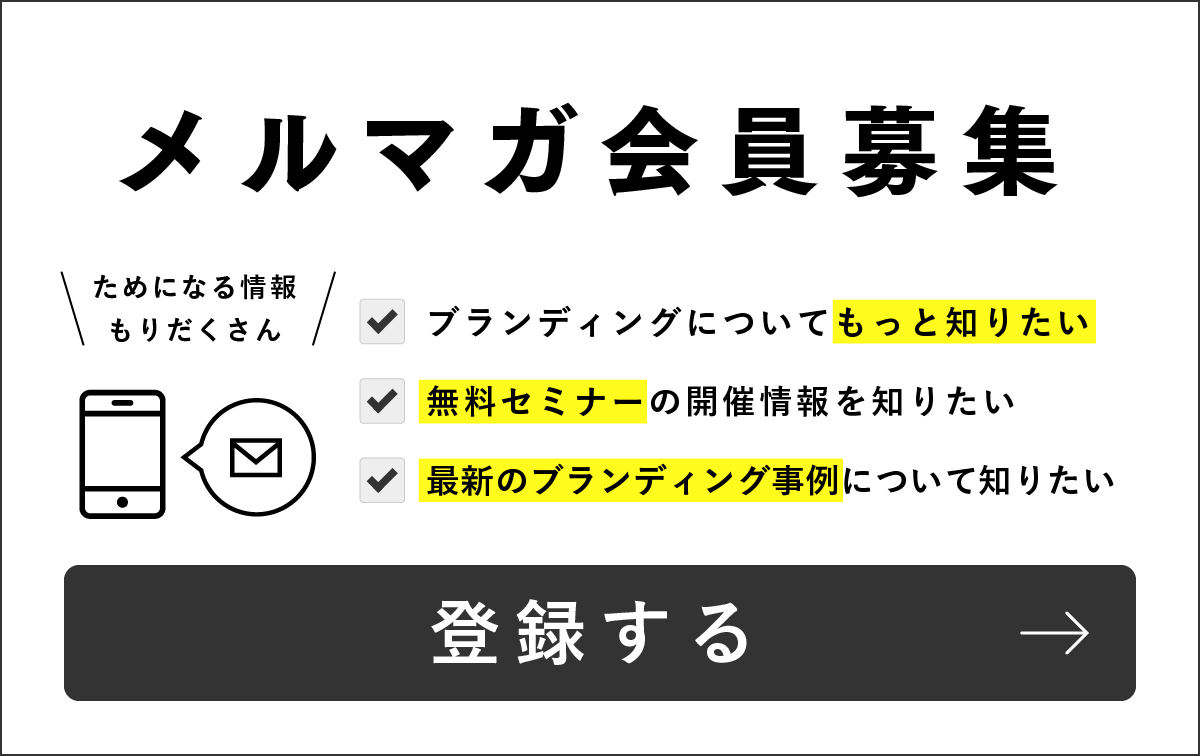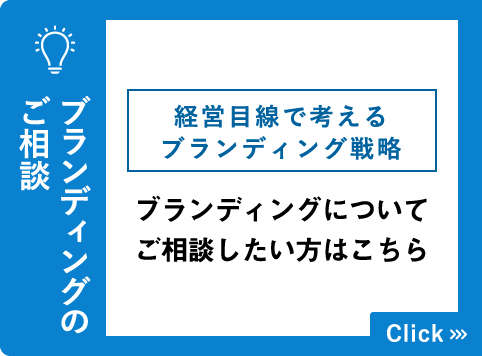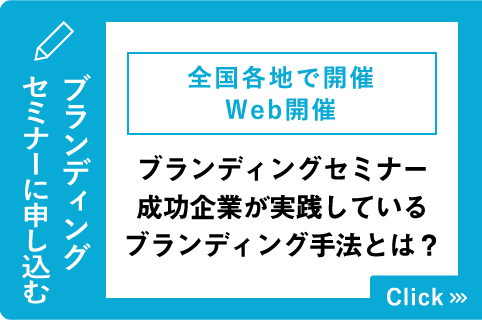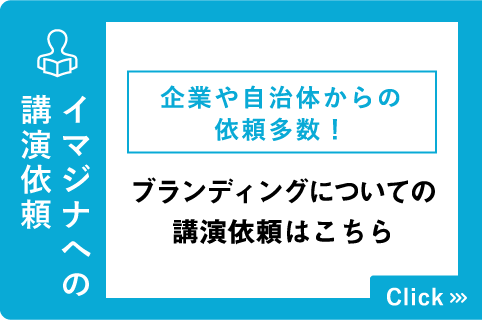社員や部下の挑戦を後押ししよう、主体的に動けるようにしようと思い、色々試してはみるものの、暖簾に腕押し、笛吹けど踊らず状態で成果を感じられない方も多いのではないでしょうか。
本日は社会心理学の観点から、いかにして部下が主体的に動けるようになるかについて紐解いていきましょう。
外的な力に影響されて態度が変化することを心理学では「態度変容」と呼びます。また、他人への言葉による働きかけを「説得」と呼ぶのですが、この「説得」に関する初期の研究では、アメリカの心理学者ホヴランドらが提唱した「メッセージ学習理論」が主流となっていました。
この理論は多くの場合に当てはまるように見え、実際に多くの現象を説明できていたのですが、実証的な研究が進む中でそれほど単純ではないことがわかってきました。
例えば、注意を引く広告が理解や記憶の程度を高めたとしても、それが説得効果と常に対応するわけではない場合があります。極端な話、メッセージの内容をよく理解していなくても、説得効果が高い場合も存在します。
そこで登場したのが、ワシントン大学の社会心理学者グリーンワルドによる「認知反応モデル」です。
このモデルによれば、メッセージが直接態度変容を引き起こすわけではなく、受け手がメッセージを受け取った後に行う”セルフトーク”が態度変容の直接の原因であるとされています。つまり、メッセージの内容そのものよりも、受け手がメッセージに対してどう感じ、どう考えたかが態度を変える主要因となるということです。
この考え方はメッセージ学習理論のすべてを否定するものではないのですが、態度変容の考え方に重要な軌道修正を加えることになりました。
説得過程における受け手の能動的な認知処理の重要性に光を当てたことで、その後の企業における人材育成やチームビルディングに大きな影響を与えました。
例えばGoogleでは、いいチームの条件として、発言が一方的ではなくて双方向のコミュニケーションがあることとしており、「あれどうなってる?」「今どんな業務をしている?」のような単なる状況確認ではなく、「あなたにとって今取り組んでいる仕事はどんな意味がありますか?」といった能動的に考えることが必要な問いかけを求めています。
「予算や納期などの制限がなかったら?」「10倍のリソースがあれば?」など、可能性を最大限に広げるような質問をしたり、部下に何か足りない要素があれば、「もう少し説明してくれる?」「具体的にどうしたい?」「もしそうするならこんな選択肢もあるけど」と、促すような質問をすることが求められます。
そうすることで部下は能動的な認知処理を自然と行うようになるのです。
部下を主体的に行動できる人材に変容させるため、「誰が言うか」「誰に言うか」「何を言うか」「どうやって伝えるか」ということももちろん重要な要素ではありますが、同時に「どう考えさせるか」ということも押さえておきたいポイントだと言えるでしょう。
Googleで上記のような「質問の内容」が重視されているのも、そういった背景があるからではないでしょうか。