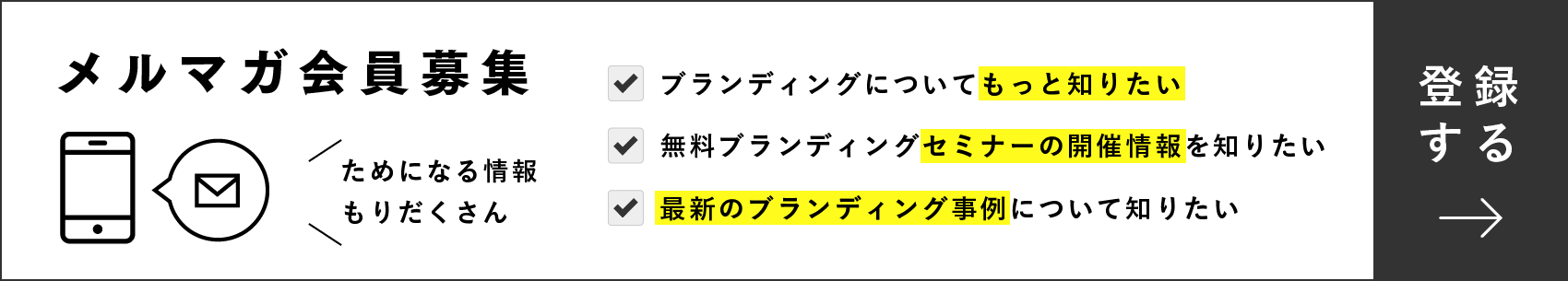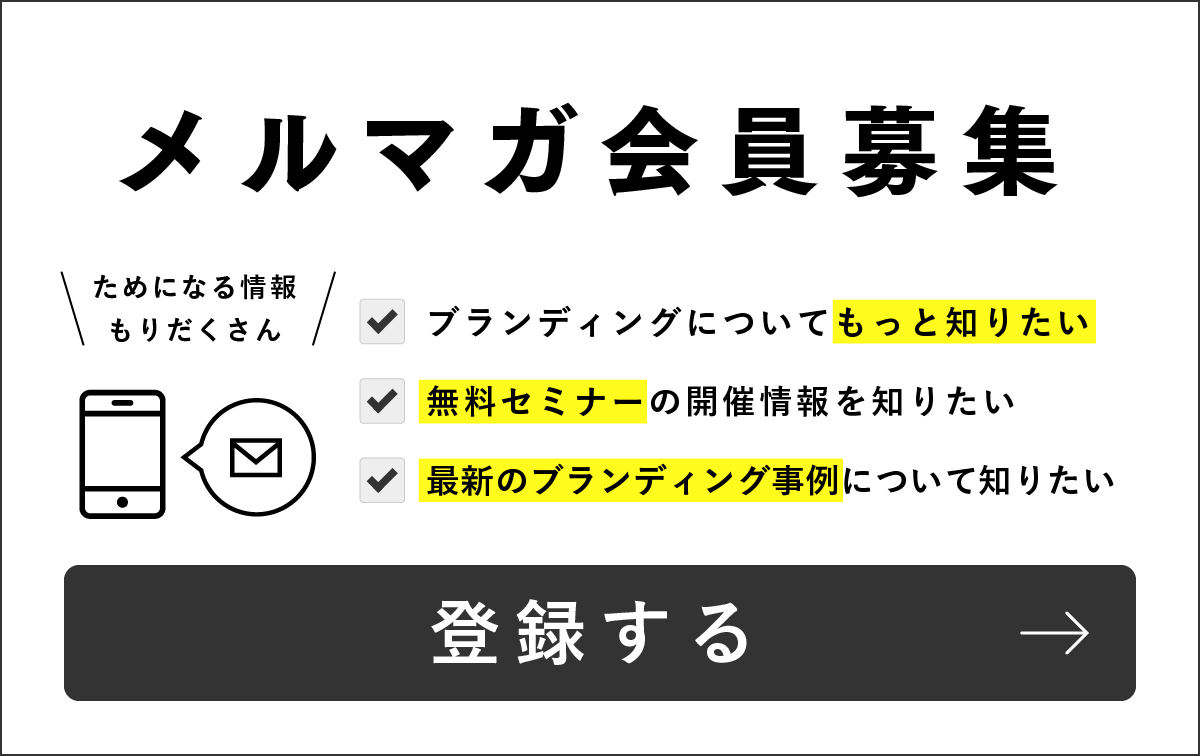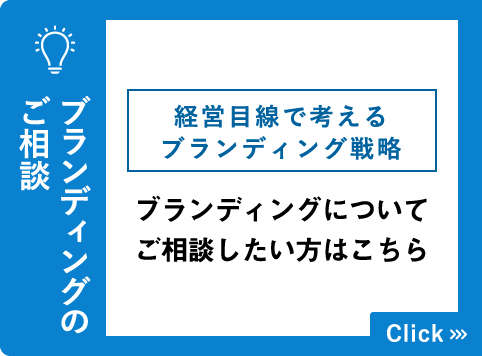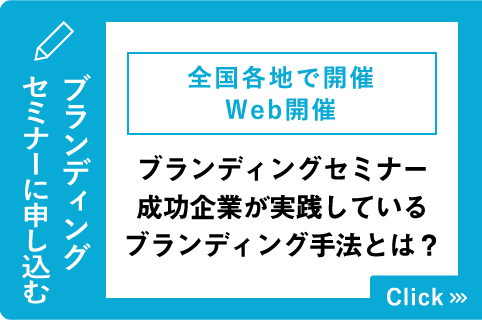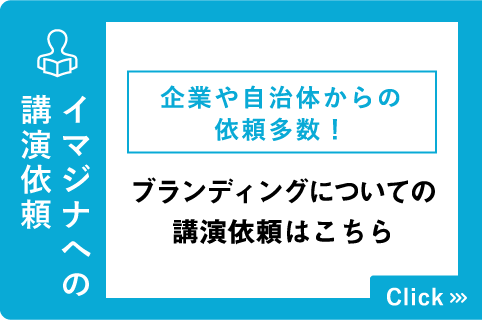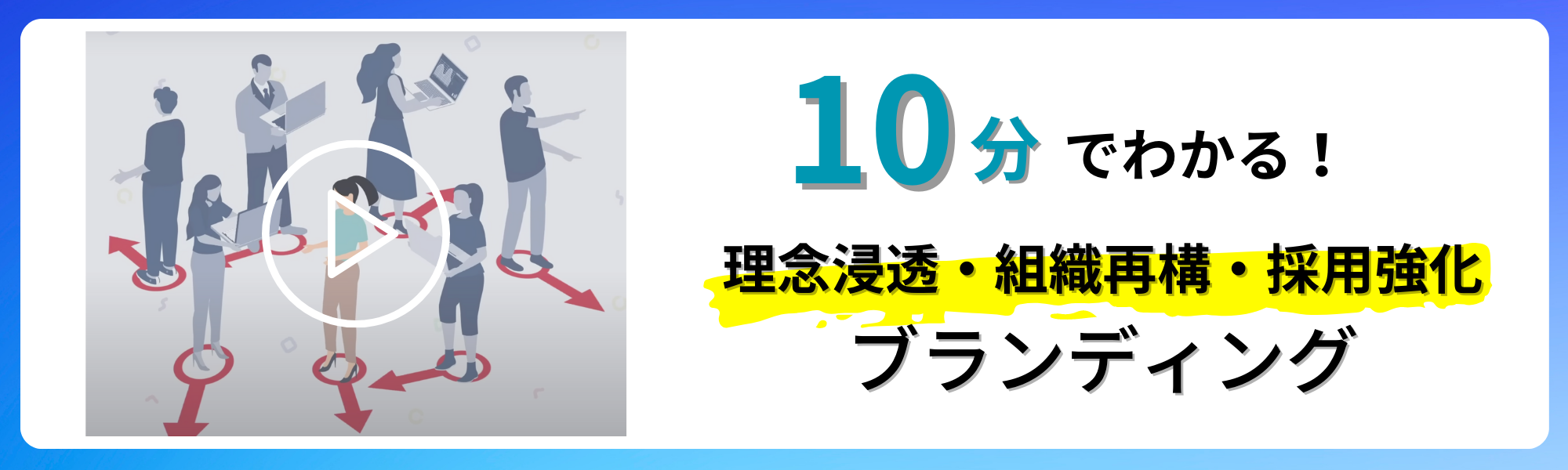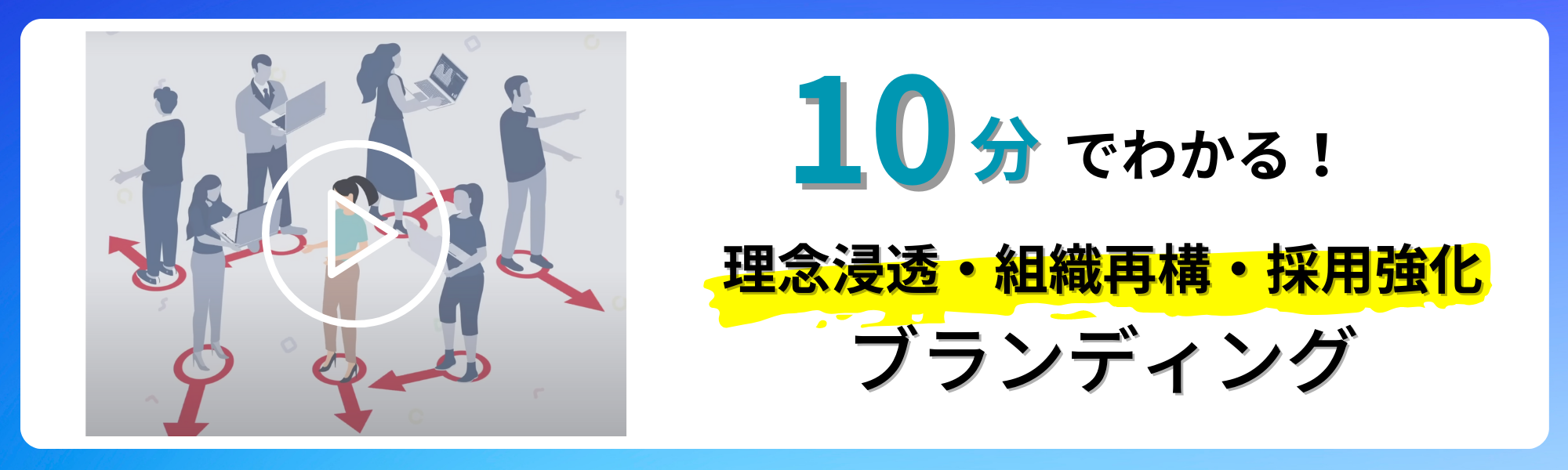自社のサービスにも活かすことができる『おもてなし』の教え
2016/07/25(最終更新日:2021/12/17)
「おもてなし」が注目されている。言葉そのものは古くからあるが、その日本ならではのコミュニケーションが脚光を浴びたのは滝川クリステル氏のスピーチがきっかけだろう。国際オリンピック委員会の総会で「自分たちにしかできないお出迎え」として「おもてなし」を流暢なフランス語で紹介したのは記憶に新しい。その効果もあり、2020年オリンピックの東京誘致は実現された。
日本で暮らしていると当たり前のように感じてしまうが、この「もてなし」の発想は世界でも珍しいものだ。来訪者を歓迎し、心ゆくまでその一瞬を堪能していただく。マニュアルには書き表せられないそのコミュニケーションの姿勢は、特筆すべき日本文化として世界に認知されるまでに至った。
この文化はサービス業、特に旅館やホテル、飲食店など接客業の文脈において用いられることが多い。そのため、それ以外の業種で働く人々にはあまり関係がないと思われがちだ。たしかに直接的に顧客とコミュニケーションをとらない業務の場合は、一見すると関係がなさそうに感じられる。
しかしもう一歩踏み込んでその「おもてなし」文化の深淵を覗くと、どんな業態や業種の仕事にも活かせる教えがあるのではないかと感じさせられる。それは単に「顧客には誠意をもって接しましょう」といった、ありがちな標語のみを指すのではない。この言葉にはさらに深みのある、含蓄ある教えが眠っていると思うのだ。
そもそも「おもてなし」はどのように発展し、日本ならではの文化として成熟していったのか。欧州をはじめとした西洋の文化と比べてみよう。もちろん、西洋には西洋流とも言える、来客者のもてなし方法がある。

欧州は階級社会である。ホテルの歴史は欧州から始まるが、旅先でホテルに宿泊できるのは一部の貴族のみであった。そのため接客を担当するホテルのバトラーは、宿泊者より格下の存在。絶対的なヒエラルキーが存在したため、宿泊客は必要以上にバトラーと接することはないし、バトラーも自ら話しかけ交流をすることはなかった。そういった環境下で評価されるサービスというのは、言いつけを正確かつ迅速に実行してくれる接客態度である。西洋のホテルでは、顧客の要望に答えることが良きサービスであり、要望が出るまではじっと待つ。要望が出たらパッと動き相手の望みを叶えることが善とされた。言うならば、これが「西洋流のおもてなし」に位置づけられるだろう。
対して日本。旅館の接客態度におもてなしが見られると思うのだが、西洋と比較すると従業員と宿泊者の関係性はもう少しフラットである印象だ。それが世間話だとしても、従業員は状況に応じて様々な観光スポットを宿泊者に提案するし、廊下ですれ違えば「今日はどこにお出かけですか」と微笑みかける。さらに顧客と距離が近づいたら、旅の目的やパーソナルな部分も自ら質問していく。積極的に宿泊者とかかわりを持ち、コミュニケーションを通じて顧客体験を追及する姿勢。これが西洋との大きな違いではないだろうか。

おもてなしといえば1つ、印象的なエピソードがある。それは安土桃山時代。豊臣秀吉は千利休に「『朝顔を眺めながら行う茶会』に来ませんか」と誘われた。利休の芸術的感性を認めている秀吉。「利休が誘うほどだから、さぞかし見事な朝顔があるのだろう」と期待して屋敷を訪ねるが、なぜか花はすべて切り取られている。どうしたことかと思い茶室に入ると、そこには一輪だけ活けられた朝顔が。質素な茶室に一輪だけ咲くその花は、決して豪華絢爛とは言えないのに、部屋全体をたしかに彩っている。わびさびの真骨頂であり源流である。これを見た秀吉は利休の美学に感嘆したそうな。これが「朝顔の茶会」という逸話だ。
この話には、時の天下人秀吉を心から迎え入れようという利休の明確なメッセージが感じられる。自身の美学を余すところなく伝え、各上かつ客人である秀吉を「良い意味で」裏切る。相手を認めた秀吉は、提示された心地よい体験に身を任せる。筆者は勝手ながら、これが日本のおもてなしの源流ではないかとひそかに思っている。
これは決して、西洋の貴族とバトラーの関係では考えられないだろう。相手の想像を超える提案をする、ここでしか感じられないエクスペリエンスを提供する。そういった取り組みが日本のおもてなしなのではないか。そしてバトラーとの決定的な違いは「おもてなしには大なり小なりメッセージが伴うもの」ということだ。
これを企業が提供するサービスに置き換えてみよう。利休は自分が培ってきた哲学と技術を秀吉に提供した。企業でいえば、自分たちが培ってきた「ならでは」の思想。こだわり。また心から誇れる技術。きっと相手が喜んでくれるだろうサービス。そういったものを精一杯顧客に提供するのが、一番のおもてなしなのではないだろうか。
これらの取り組みは一朝一夕にできるものではない。まず自分たちの強みを見極め、それを明文化し、社内に発信しなければならない。組織の構成員に自分たちの強み、文化、提供すべきもの、あるべき姿を余すところなく伝え、腹落ちさせる。そして、それを外部に提供するサービスと連動させる。従業員の言動と提供するサービスが一致したとき、「らしさ」が明確に顧客に伝わり、企業独自の強みが形作られていく。
歴史を振り返ると、自分たち流のおもてなしを武器にしてエクセレントカンパニーを創造した会社は数多くある。ウォルマートやディズニー、スターバックスコーヒーなど。グローバル化が叫ばれる今、日本企業が当たり前に行ってきた「おもてなし」は大いなる武器になるのではないか。
その思想は単に、表面上の人当たりの良さを指すのではない。自分たちの文化やサービスを見極め、それを基軸に相手の期待を超えるサービスを提供する。それが本質的なおもてなしだと思う。
日本企業のブランド力低下が叫ばれているが、再興のカギはすでに持っている日本文化に隠されているかもしれない。何が提供できるのか。何を提供することで、かけがえのない強みを創造するのか。今一度、自分たちができる「おもてなし」を見直してみたい。